序章
ある地方の小さな町。夜になると、町の人々は決して一人で郵便受けを開けないという奇妙な言い伝えがあった。
「夜に届く手紙は呪われている」と。
若い女性・美咲(みさき)は、都会からこの町に引っ越してきたばかりだった。田舎の静けさを気に入り、古びた一軒家を借りた。近所の人々は親切だったが、どこか不自然に夜の郵便受けを避けるような素振りを見せることに違和感を覚えていた。
奇妙な手紙
ある夜、美咲は仕事から帰宅し、ふと郵便受けを覗いた。そこには、古びた黒い封筒が入っていた。差出人の名前はなく、宛名も滲んで読めない。
「誰かのいたずら?」
そう思いながら封を開けると、中には白い紙が一枚。そこには震えた文字でこう書かれていた。
「助けて」
背筋が凍った。ぞっとしながら周囲を見渡したが、人気はない。美咲は恐る恐る家の中へ入り、手紙を机に置いた。だが、気になって眠れない。
翌朝、もう一度手紙を確認しようとすると、それは消えていた。
次々と届く手紙
それからというもの、毎晩、同じ黒い封筒が届くようになった。中身はいつも短い言葉だけ。
「ここにいる」
「寒いよ」
「見てるよ」
美咲は怖くなり、隣人の老婦人に相談した。老婦人は顔を曇らせ、静かに語り始めた。
「昔、この町で少女が一人、夜に手紙を出しに行ったまま戻らなかった。そして、その夜から毎晩、黒い封筒が届くようになったのよ」
美咲は血の気が引いた。「その少女は……?」
老婦人は首を振るだけだった。
最後の手紙
ある晩、美咲は意を決して、夜の郵便受けを覗くことにした。いつもの黒い封筒が入っていた。震える手で開くと、そこには——
「後ろを見て」
美咲は凍りついた。
ギシ…ギシ…
背後で何かが軋む音がした。振り向きたくない。しかし、足が勝手に動く。
そこには、真っ黒な影が立っていた。
不気味なほど長い手が、美咲の肩にそっと触れ——
その瞬間、美咲の意識は暗闇に沈んだ。































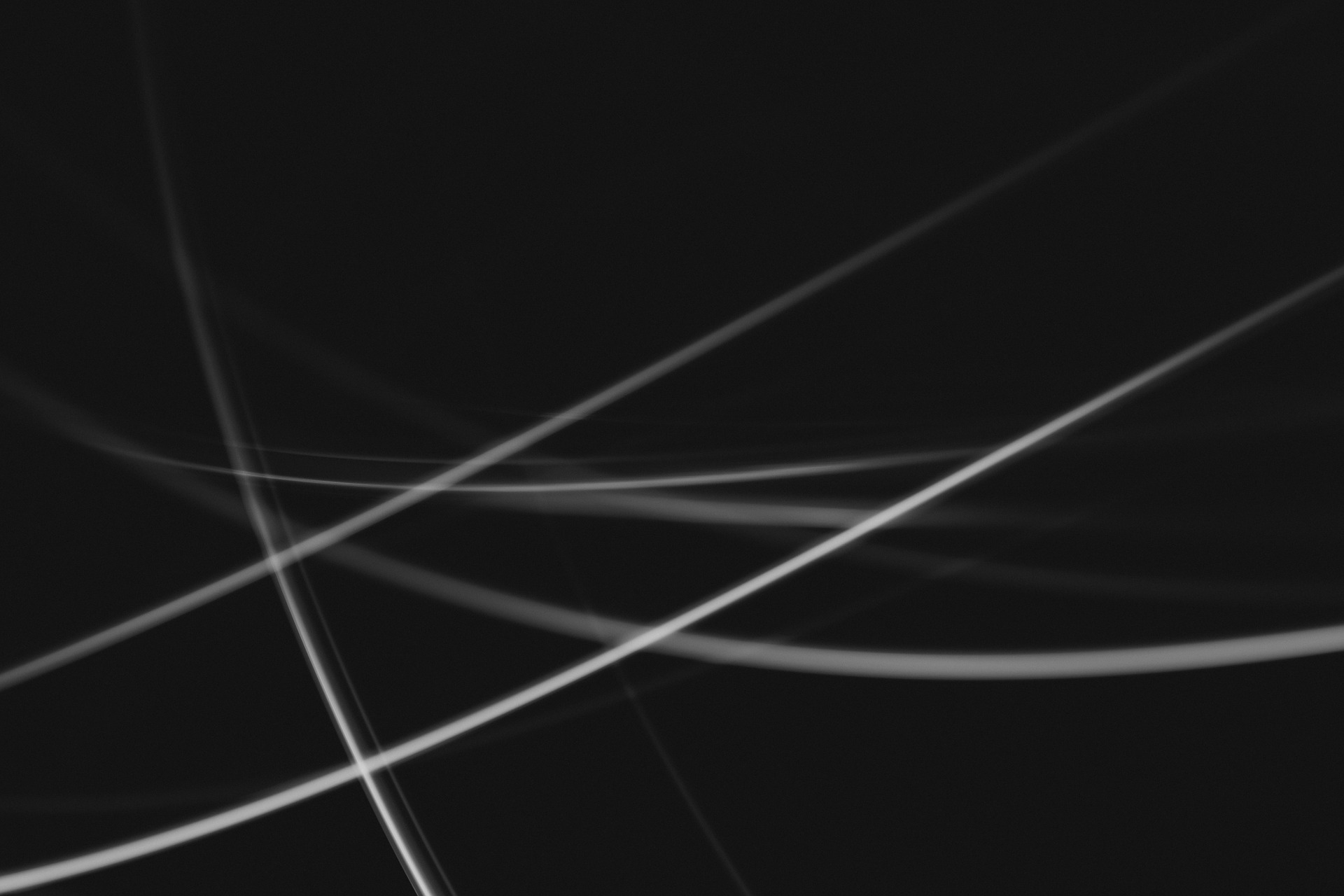







※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。