K子さんにとって運転免許証というのは車を運転できる証というだけではなく、見る度に強烈な思い出が蘇る特殊なカードでもあるという。
若かりし頃のK子さんが免許取得の為に通っていた教習所は辺鄙な場所にあり、いつもバスで通っていた。
順調に仮免を取得し、1回目の路上教習で担当になった教官がやっかいな人だった。
身長は平均位だが体格はラグビー選手のようにガッチリしている40前後のその教官は小柄で華奢なK子さんを気に入ったらしく、運転中に教習とは関係ないプライベートな事を根掘り葉掘りひたすら聞いてくるのだ。
K子さんは適当に相槌を打ちながらあしらい、次回以降はこの教官に当たらないようにと胸の内で祈った。
それ以降奇跡的に4回目までは別の教官が担当したのだがついに5回目で祈りの効力が切れたのか、例の教官が担当になった。
「じゃあ今日はこのルートを走ってみようか。」
出発前に地図で道順を確認し、一通り頭に入れた所で車を発進させる。
右折左折、車線変更もスムーズに行いながら田舎の街を10分程走らせて赤信号で止まった時だった。
シフトレバーを握っているK子さんの手の上に教官は自身の手を重ねてきた。
「なあK子。俺本気なんだよ。わかるだろ?この前の返事、聞かせて欲しい。」
先日、帰り際この教官に口説かれ、夕食に誘われていたのだ。
ここではっきり言わないとダメだと思い、k子さんは手を振り払い教官の目をしっかり見ながら告げる。
「ごめんなさい。そういうの本当に迷惑です。やめてくれませんか。」
教官は一瞬目を見開き、「そうか」と一言呟いた後、フロントガラスに向き直った。
それから車内に嫌な空気を充満させながらそのまましばらく走行を続け、車は民家の少ないのどかな田園地帯に入る。
踏切を渡っている途中でいきなり車が急停止し、k子さんの胸にシートベルトが強く食い込んだ。
何事かと隣をみると教官が助手席の補助ブレーキを踏み込んでいる。
「なあ、k子。さっきの事、もう一度よく考えてくれないか。」
なんてしつこい男だろう。
「何度考えても同じです。私は、教官とはそういう仲になれません。」
毅然と口にするk子さん。
「ああ、そうか。つまり、俺はフラれたってわけか。なるほどね。……じゃあ、しょうがないよな。」
カチャリ。
「……え?」
ハンドルを握るk子さんの左手首に手錠がかけられた。
もう片側は教官の右手首に繋がっている。
「君に否定された俺にはもう生きる意味は無いんだ。何もかも全て…終わりだ。うん。」
「ちょ、冗談はやめて下さい!」
k子さんは全身から血の気が引いていく。

































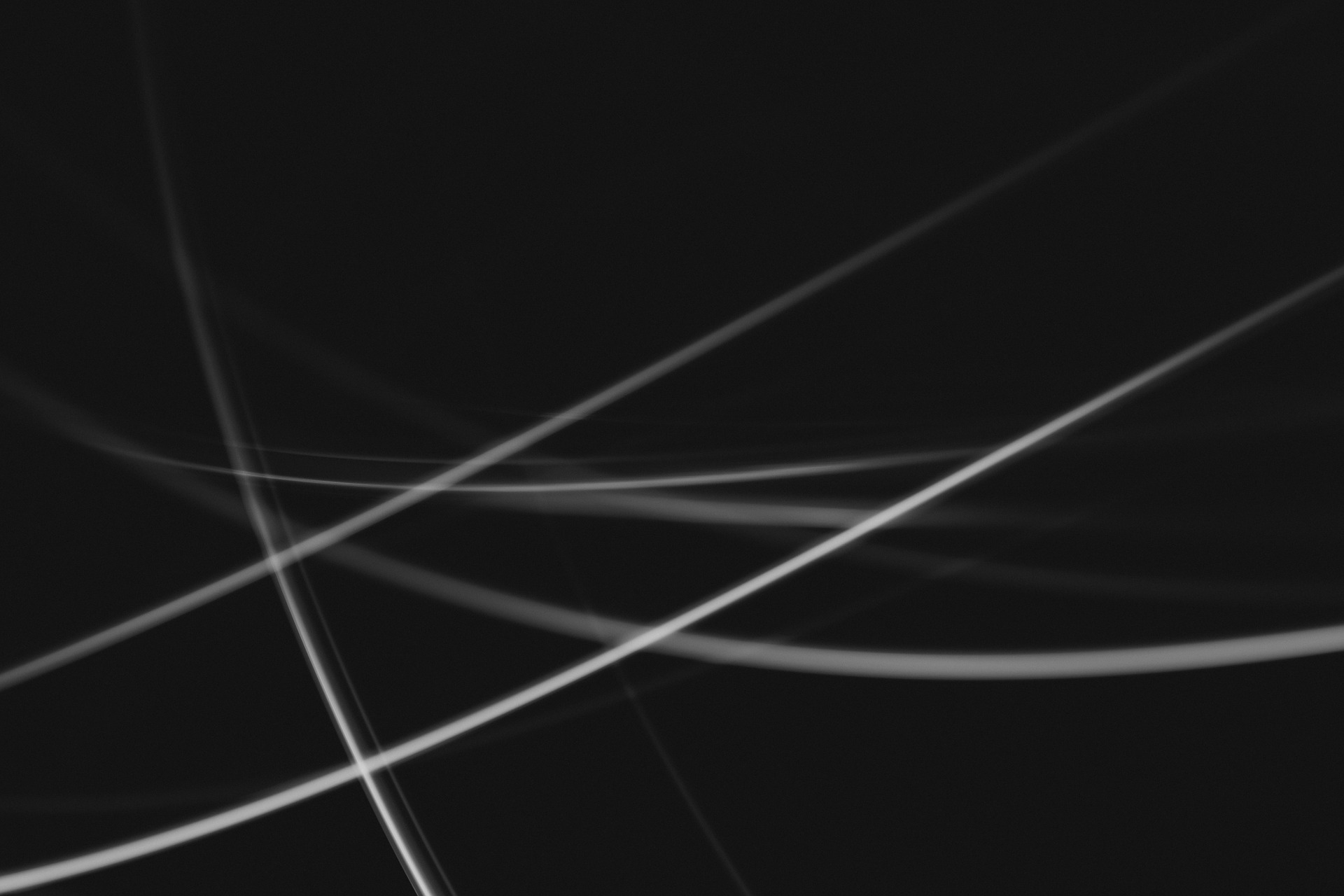








ハラハラドキドキ助かって良かった。
メンヘラマッチョはえぐいw
最低な教官、自業自得だよ死んだのは