「―――――はい、はい。どうも。ええ、それじゃあよろしく。」
カシャンという受話器を置く音が聞こえた。祖母が誰かと電話していたようだ。階段を下りる音に気付いたのか祖母がこちらを向いて言った。
「紀一郎、起きたのかい」
「ああ、ちょっと腹が減ってさ。なんかある?」
祖母はため息をついて呆れた調子でこう返した。
「なァ紀一郎、お前、なんかあったのかい?」
その言葉に俺は間髪入れずに答えた。
「なんかあったもなにもないだろ!」
祖母は純粋に心配してくれているのだとわかっていながら、俺は声を荒げてしまう。
「・・・ごめん。なんでもない」
もう寝るよ、おやすみとそれだけを告げて、俺は呼び止める祖母の声を無視して二階に上がった。
〇
11月20日 午後10時ごろ
俺は事前にまとめてあった荷物と冷蔵庫に入っていたおにぎりを一つ手に持って外へ出た。祖母はいつも夜9時には床に就くので、この時間に出かければ気づかれることはない。外の空気は凛と張りつめていて、吐く息が白い。俺は腹に入れることだけを考えて、おにぎりにかぶりついた。かつて、戦乱の世に奇襲を行った武士たちも、今の俺と同じ気持ちだったのだろうか。俺は武者震いをして自転車にまたがった。
叔父の家はここから自転車で一時間半ほどのところにある。距離にして二十キロ弱といったところだろうか。別に何キロだっていい。何時間かかろうとも、俺はそこへ行くのを厭わない。計画は今、折り返し地点にある。最後は新神主を祝う祭りで、あいつを直接射抜いてやる。この祭りは岩祭家独自のもので、いわばお披露目会のようなものだ。開催は明日土曜日。祖母のカレンダーを見て確かめたので間違いない。俺はまだ参加したことはないが、父は祖父が神主になった際にその祭りに参加させられたとよく言っていた。地元の人間はもちろんのこと、全国各地から親族が集まることだろう。そんな大勢の人間に囲まれて、あいつは死ぬのだ。
「フッ、フヒヒッ」
自分でも気持ち悪いと思うような笑い声が喉からかすれるように漏れ出す。ああ、なんていい気味なんだ。これで俺は、岩祭家の当主になれるッ!
そんなことを考えながら、疎水に架かる橋を渡った時だった。後ろからパトカーのサイレンが鳴ったと同時に、拡声器から発せられる雑音交じりの声で呼び止められた。本当に最悪なタイミングだと思った。自転車を停めて待っていると、黒のセダンがゆっくりと横に停車した。意外にもそれは覆面パトカーだった。ドアウィンドウが下ろされる。
「きみ、中学生? こんな時間に危ないでしょう」
そこにいた男に俺は見覚えがあった。確か、木元とかいう刑事だ。俺は鼓動が激しくなるのを感じた。
「・・・すみません」
どうやら相手は俺に気付いていない様子だった。俺は次に来る質問に備え、頭の中のギアをフルノッチで加速させた。
「あのね、最近ここらへんで妙な事件が立て続けにおきているんだよ。親御さんが心配するから早く帰りなさい」
「わかりました、すみませんでした」
刑事はそれを聞くと、じゃあ気を付けてと言って車を発進させた。
そうか、俺は今ネックウォーマーを身に着けている。それにここは街灯も少なくて妙に暗い。だから気づかれなかったのか。俺は今が冬であることを幸運に思った。それからは何事もなく、叔父の家までたどり着いた。途中、道の上にカカシが置いてあるのを見た気がするが、まあ気のせいだろう。叔父の家が見える高台を見つけ、そこで火箭と弩を取り出す。
「スーゥハァ、スーゥ」
とっくのとうに自転車を降りたはずなのに息が上がったままだ。ここまで来て、俺は緊張しているのだろうか。気を紛らわせようと、俺は自分の頬を引っ叩いた。
火をつける前に、弩に火箭をセットして、叔父の家を狙う。叔父がいると思われる二階の角部屋には、煌々と明かりが漏れ出していた。大丈夫だ。俺にならできる。そう確信して、俺はライターを取り出した。シューッという音を立てて導火線に火が付く。
































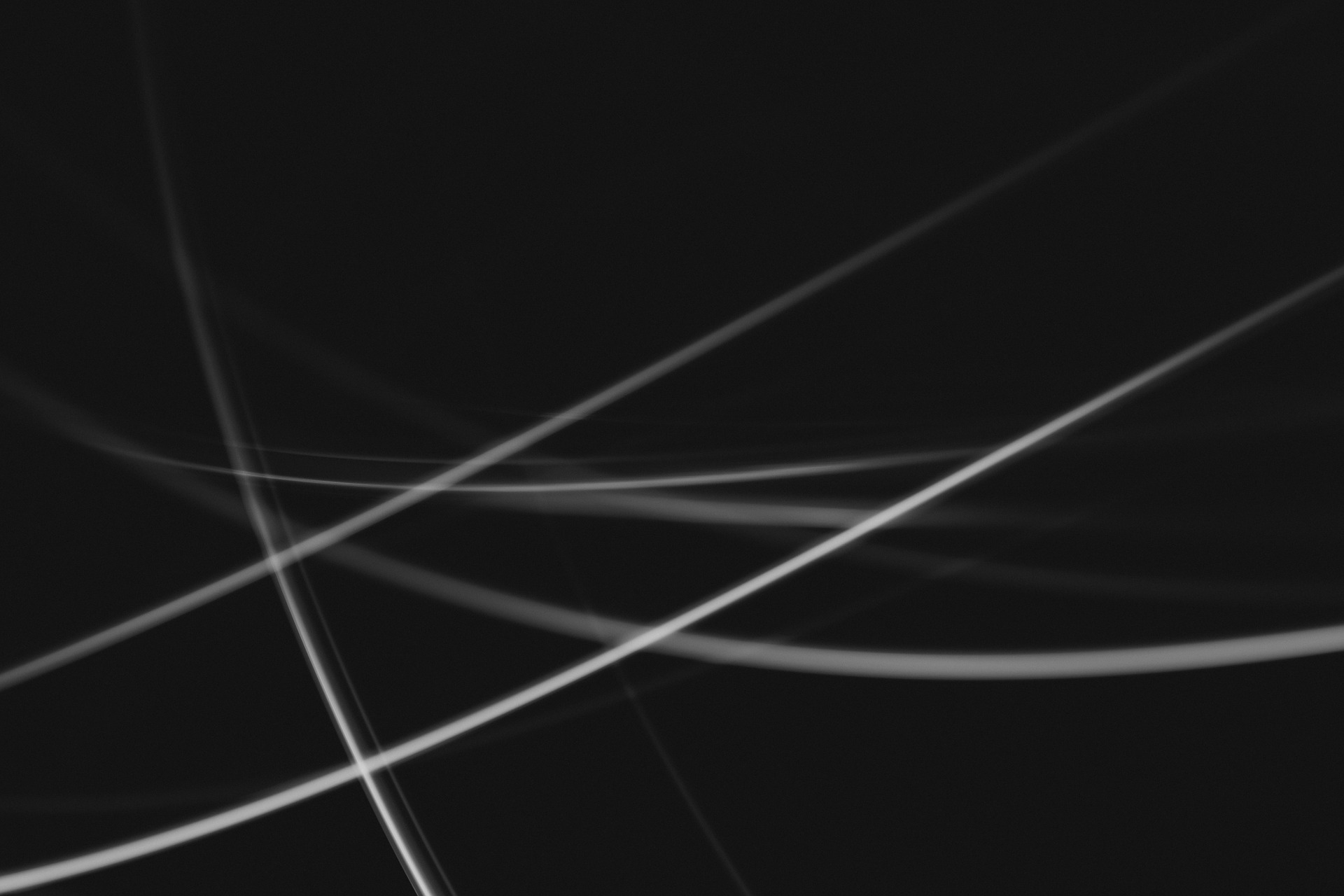







文章が綺麗でストレス無く読めました。
素晴らしい作品だと思います。