我が岩祭家は、戦国時代より続く萩島の豪家だ。もとは武家として栄えたが、江戸時代初期、萩島の象徴ともいえる飯倉神社の家系が断絶されたことを機に、神職へと転身し、代々この地を治めてきた。岩祭家が萩島の安寧を祈る気持ちは今も昔も変わらない。お前もゆくゆくは飯倉神社の神主として、萩島の人々の心の拠り所となり、その発展に貢献しなさい―――――
俺は幼少の頃から祖父にそう教わってきた。祖父はとても優しく、そして強い人だった。その言葉を胸に、私はこれまでどんな苦境に立たされようとも努力を惜しまず、次期岩祭家の当主としての自覚を保ち続けてきた。中学校を卒業する頃には弟もでき、そこに兄としての自覚も加わった。親からとやかく言われたからとか、世間体を気にしていたからとかそんなものではなく、岩祭家を守りたい、萩島の地を守りたいという純粋な気持ちの表れだった。弟の誕生で我が家には新たな活気が生まれ、笑顔の絶えない日々が続いた。これからもこんな平和な日常がずっと続くものだと信じていた。そんな岩祭家に、暗雲が影を落とし始めていることに俺は気づく余地もなかった。
〇
一か月前、祖父の善一郎が亡くなった。それはあまりにも突然のことだった。ようやく夏の暑さから解放され、少し肌寒さを感じさせるようになった秋の早朝。ドタドタと廊下を慌ただしく走り回る音で目が覚めた。何事かと下に降りた時、俺は状況をすぐに察した。いつも冷静なあの母が目に見えて取り乱している様を俺は初めて見た。
享年76歳。心疾患による突然死だった。葬儀はその後、すぐに執り行われた。祖母や母は今朝とはまた違った意味で慌てていた。俺には弟の面倒を見るくらいしかしてやれることが無くて、こんな時に子供はつくづく無力だなと悔しかったのを憶えている。
葬儀には多くの人間が参列したが、豪家とは言え、バブル時代の崩壊も相まって残された財産は限りあるものだったので、資産争いなんてものは起こりようもなかった。問題は飯倉神社の後継者だ。通常であれば、長男である父が神主を引き継ぐ手はずになっていたのだが、祖父の遺言に父・弥一郎の名はなかった。代わりに書かれていたのは、二人でよく話し合えという内容だった。二人というのは、父とその弟である久彦叔父さんのことだ。叔父は大学時代に家を飛び出したきり、今日に至るまで萩島の地を離れ、大学で歴史学を研究していた。以前、何かの集まりで顔を合わせたことはあったが、叔父は一族のしがらみを嫌い、いつか当主になることを夢見る俺を憐れむような目で見ていたのを今でもよく憶えている。
そんな叔父が、祖母によって遺言書が読み上げられた後、「俺は当主を請け負うつもりだ」と静かに言い放ったのを聞いて、俺たちは言葉を失った。のちにそういう状況を青天の霹靂というのだと知った。叔父はもちろんそんなものには興味がないと一蹴するはずだと、一族の誰もが思っていたのだ。そこからは地獄のような言い争いが続いた。これまで家のことを何一つせず、自由に生きてきたくせに権力だけは欲しようとする。そんな叔父のことが父は許せなかったのだと思う。当たり前の話だ。あんな声を荒げて怒り狂う父を見たのはこれが最初で最後だった。祖母の鶴の一声でなんとかその場は収まり、後日、再び話し合いが行われる運びとなった。
父は地元の商工会や知り合いの弁護士、中には代議士にまで話を持ち掛けて、入念に準備をしていた。最悪の場合、裁判を起こす気だったのだと思う。父の鬼気迫る顔に俺はそらおそろしいものを感じた。その矢先、事件は起きた。
〇
11月6日 午後2時33分
その日、高校受験を控えた俺はいつも以上に勉学に打ち込んでいた。こんなことで父に心配をかけるわけにはいかないという思いと、子ども特有の潔癖から生じる、どろどろとした大人の争いから目を背けたいという二つの思いが、それを加速させていた。そんな中、教室で授業を受けていた俺を担任と教頭が慌てふためいて連れ出し、こう告げたのだ。
父が自殺を図った、と。
到底、そんなことは信じられなかった。数日前まであんなに意気込んでいたあの父が自殺なんてするはずがない。目の前が真っ白になった。それを見ていたクラスメイト達が一斉にどよめき始める。しかし、俺の耳には全く響いて届いていなかった。「とにかく今は一秒でも早くお父さんの元へ行ってあげなさい」という教頭の言葉になんと返事をしたかさえ覚えていない。
おぼつかない足取りで帰宅した俺を待っていたのは、暗い顔をした祖母だった。まだ三歳にもなっていない弟は何が起こったのか理解していないようだった。お気に入りの犬のぬいぐるみを片手に、口をぽかんと開けてこちらを見ている。その無垢な様子が余計に辛くて、俺は歯を食いしばった。そんな弟に目もむけず、祖母は顔をしかめて言い放った。
「跡継ぎは久彦にやらせる」
〇
叫びにも嗚咽にもならない声を出して、俺は家を飛び出した。そのあとのことはよく覚えていない。気が付くと俺はベッドに横たわって、無機質な天井を眺めていた。そこは病院のようだった。左腕から点滴のチューブが伸びている。医者の話によると、俺は近くの川でおぼれていたところを通行人に発見され、一命をとりとめたらしい。意識がはっきりするにつれ、いっそ死んでいた方がマシだったという思いが俺の胸をいっぱいにした。
しばらく経ったころ、俺のもとに警察がやってきた。こんな状態の俺に事情を話せと言うからその訳を聞いたところ、祖母が頑なに口をつぐんているらしい。木元と名乗った刑事は、俺に続けてこう言った。
「君のおばあさんには口止めをされたんだけどね、これは伝えておかないといけない」
今日の昼頃、父は母とともに夏目湖近辺の崖から車ごと飛び降りたらしい。遺書などは見当たらなかったが、現場の状況からして事件性はないと警察は判断したようだ。不幸中の幸いともいうべきか、意識不明の重体というだけで、父と母は生きていた。市内の大きな病院で手当てを受けているという。面会にはまだ少し時間がかかると刑事は告げた。俺は少しばかり安堵すると同時に、先ほどの祖母の様子を思い返す。身内から自殺者が出たとなれば一族の恥。それどころから母を道ずれにしたというのだから最悪、殺人者にもなりかねない。祖母が俺や弟にも冷たかった理由はこれだったのかと理解した。
「とりあえずまた後日、話を聞かせてください」
そう言うと木元は足早に病室を後にした。木元が去ってから、俺は考えるのをやめられなかった。頭の中に黒々としたものが芽生えだす。父が自殺なんてするわけがない。あいつがやったんだ。あいつがやったに違いない。あいつが、あいつが父と母を・・・。
その時、俺は復讐を誓った。
〇
11月7日 午前10時41分
特に目立った外傷も見られず、俺は翌日には退院することができた。金は寝ている間に祖母が払っていったそうだ。迎えには誰も来なかった。「若いっていいわねぇ。でも、こんなこともうしちゃだめよ?」という看護師の言葉に俺はうなずくことが出来なかった。
家へ帰ると、見知らぬ車が二台、玄関先に停められていた。居間から聞こえてくる声に、それがすぐに叔父の車だとわかった。瞬間的に殺意が芽生えるのをぐっと抑え、俺は廊下を進んだ。
「やあ、紀一郎君。オヤジの葬式ぶりだね」
居間の横を通った時、叔父がこちらに手をあげて声をかけてきた。隣には叔母がいて俺に軽く会釈する。叔父の前には、祖母と弁護士の男が座っていて、机の上には様々な書類が並べられていた。この弁護士は父と懇意にしていた仲田という男だ。俺はそれを一瞥すると何も言わずに自室へ向かった。































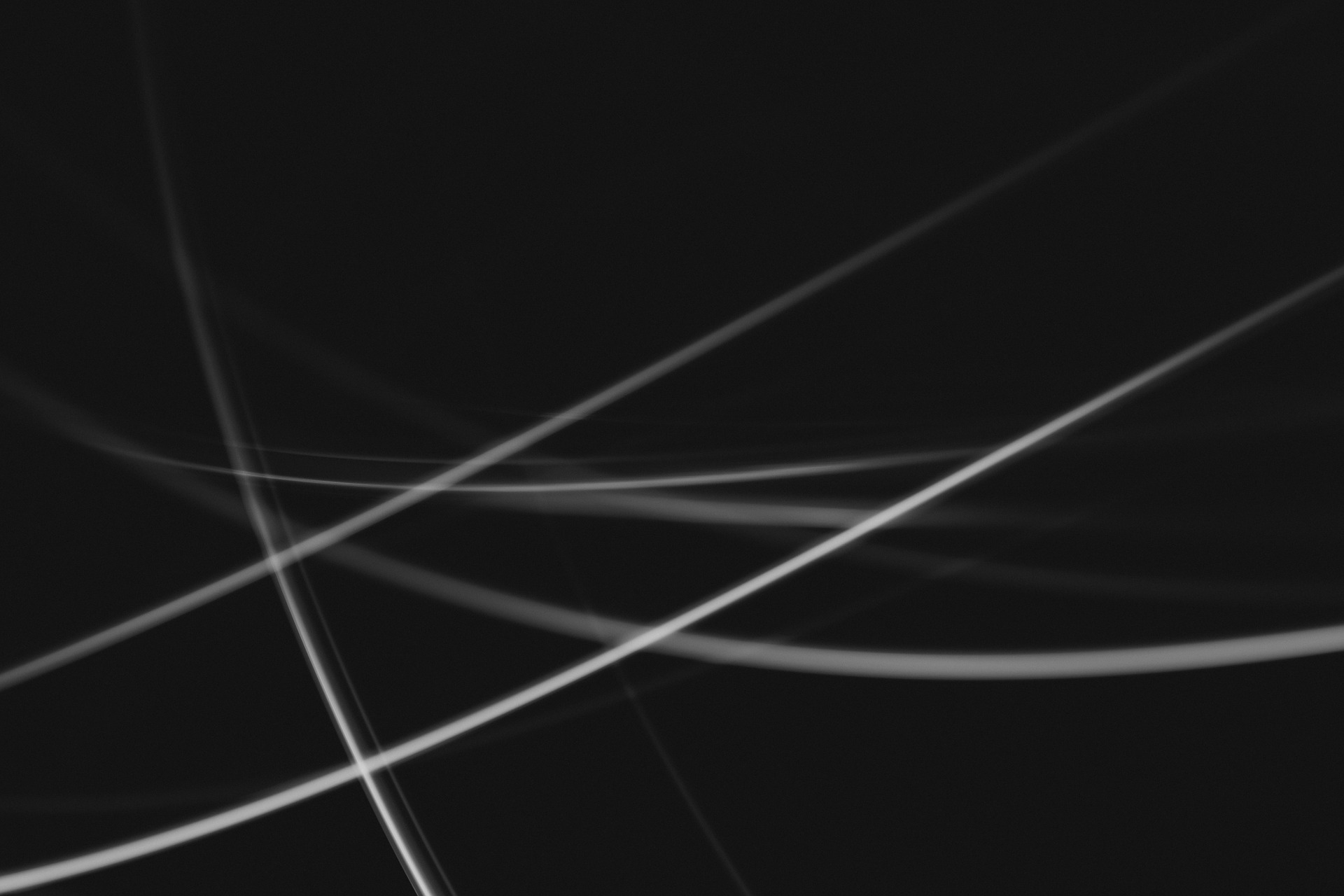









文章が綺麗でストレス無く読めました。
素晴らしい作品だと思います。