その日見た夢の内容は、よく覚えている。
どこかの外出先で、私は恋人と遊び呆けていた。それはとても穏やかで、幸せな時間と形容して間違いないひと時だった。
しかし、何かのタイミングで、私はこの世界が夢の中だと気付いてしまったようだ。
残念ながら、目覚めるときにはこの世界と別れなければならない。折角幸せな気分に浸っていたのだが、仕方あるまい。大体こんなことを考えていたように思う。
その瞬間、夢の雰囲気が一変した。
周囲のあらゆるものの視線が、一気に私のもとに集まる。風景の一部として存在していた全てが、私をじっと見つめる。
それはまるで、気付いてはならないタブーに私が気付いてしまったかのような、冷たい視線だった。
そして、私の周囲にいた全ての人間が、私に向かって歩き始めてきたではないか。恋人も、周囲の無関係な者も、歩み寄るすべてのものの表情には穏やかさなど欠片もなく、私に対する敵意のみが渦巻いていた。
私は戦慄した。いくら夢の中とはいえ、このまま接近を許すと、恐ろしいことになりそうな気がする。一刻も早く、目覚めなければ。私はその努力を試みた。
次第に、聞き慣れた日常の音が聞こえてくる。良かった、何とか現実の世界へ戻ることが出来そうだ。
所詮、夢は夢。一旦目覚めてしまえば、何も恐れることはないのだ。
しかし、私は聞いてしまった。いざ夢の世界から去ろうとする瞬間の、恋人の声を。
「貴方って、本当に夢から覚めたことがあるの?」
聞き慣れたはずの声なのに、地の底を這うように低く響く声だった。私はその真意を問おうとしたが、夢の世界は私を手放したらしい。次第に周囲のうごめきとおぞましい音がフェードアウトし、そのまま目を覚ましたのだった。
目覚めたとき、私はソファーの上にいた。傍では同居している恋人が、掃除をしているのが見える。どうやらいつの間にか昼寝していたらしい。
「どうしたの? ずいぶんうなされていたよ」
笑いながら話しかける恋人は、確かにいつもと変わりない姿で、変わりない声を発していた。
夢の輪郭は、日を追うにつれてぼやけていくものだ。
それなのに、この夢はいくら時間が経っても色褪せることなく、それどころかより鮮明な記憶となり、今もはっきりと残ったままだ。
あれ以来、私はふと考えることがある。
もしかしたら、私が生きているはずのこの世界も、夢の世界なのではないだろうか。
そうだとしたら、私がそれを強く意識した途端、ここにある世界中の万物が、今度こそはとばかりに表情を一変させ、その時こそ私は本当の恐怖を見ることになるのかも……。





























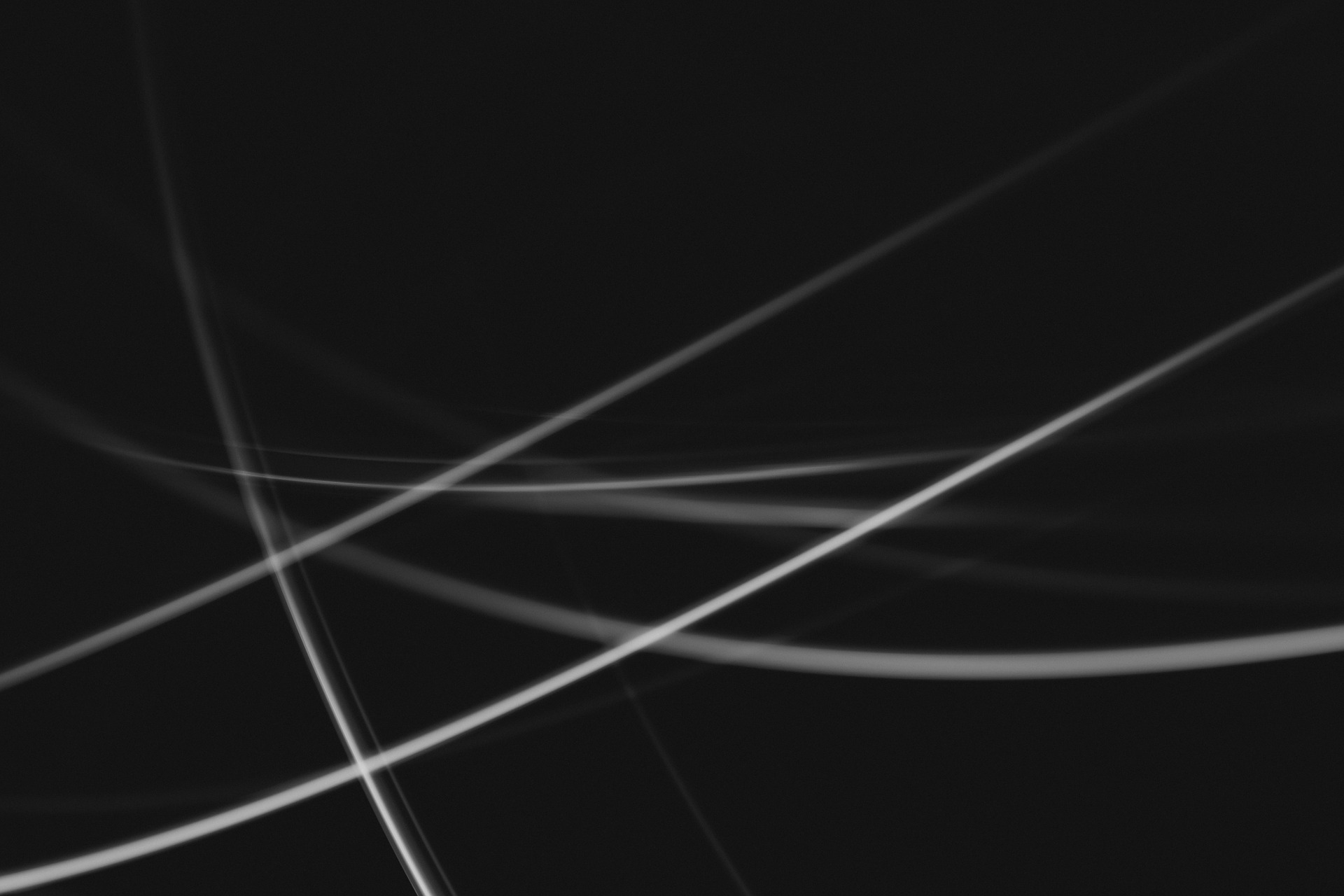







すごく怖くて面白かったです。
一回あった
夢の中で「夢」って気づいた時、突然敵(?)に襲われて逃げて、家に帰ったら目が覚めた、みたいな
夢見たことがある
実は今いる世界は夢でシュミレートしているだけなのではないかって時々思う事ありますよね。
「水槽の脳」やTVゲームの「サイコブレイク」など夢を扱った思考や作品はたくさんありますしね。
次の瞬間、夢から覚めて今までのは現実ではなかったと認識するのかも知れません。
怖い…
でもまだ夢で良かったですね。
「人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢 幻の如くなり」 夢 幻 と現実の違いは意外と曖昧だから「引寄せの法則」だのの類いも売れる