江戸のとある夏の夜、武家屋敷の一角に、十人の男たちが集まっていた。彼らは剣術の達人、商人、浪人、そして旅の僧侶。誰もが「百物語」に興味を持ち、恐怖を楽しむためにこの場に集まったのだ。
部屋の中央には、百本の蝋燭が灯されている。話が一つ終わるごとに一本の蝋燭を消し、百の怪談を終えたとき、本物の妖が現れるという——それが百物語の掟だった。
一人目の男が語り出す。
「これは、俺の故郷で実際に起こった話だ……」
彼の語る怪談は、村の井戸から夜な夜な女の泣き声が聞こえるというものだった。その井戸を覗いた者は、次の日には姿を消し、決して戻らなかったという。
二人目、三人目と、次々に怪談が語られる。刀鍛冶の幽霊、夜道で振り返ると消える女、神社の古びた狐面に宿る呪い……。
蝋燭が消えるたび、部屋は闇に包まれていく。
五十話を超えた頃、妙なことに気づいた者がいた。部屋の隅に、見覚えのない男が立っているのだ。
「おい、お前は誰だ?」
浪人が問いかけると、その男は静かに微笑んだ。
「……私も話してよいか?」
誰も彼が入ってくるのを見ていない。それでも、百物語の掟に従い、彼の話を聞くことにした。
男の語ったのは、ある貴族の館で行われた百物語の話だった。その館では九十九話目が終わったとき、誰かが扉を叩いた。開けてみると、そこには誰もいなかった——ただし、部屋の中には「新たな客」が増えていたのだ、と。
その言葉に、男たちは背筋を凍らせた。
「さて……そろそろ九十九話目か」
気づけば蝋燭はあと二本。
最後の話を語ると、本物の妖が現れる。
誰もが恐れ、誰もが沈黙する中、不意に蝋燭がひとりでに揺れ——一本、ふっと消えた。
残るは一本。
そのとき、見覚えのない男が不気味に笑った。
「これで、百話目だ……」
次の瞬間、部屋の中にいた者たちは、一斉に悲鳴をあげた。
翌朝、その屋敷には誰の姿もなかった。ただ、百本の蝋燭が、一本残らず消えていただけだった。
それ以来、その屋敷では決して百物語をしてはならないと、語り継がれることになった——。
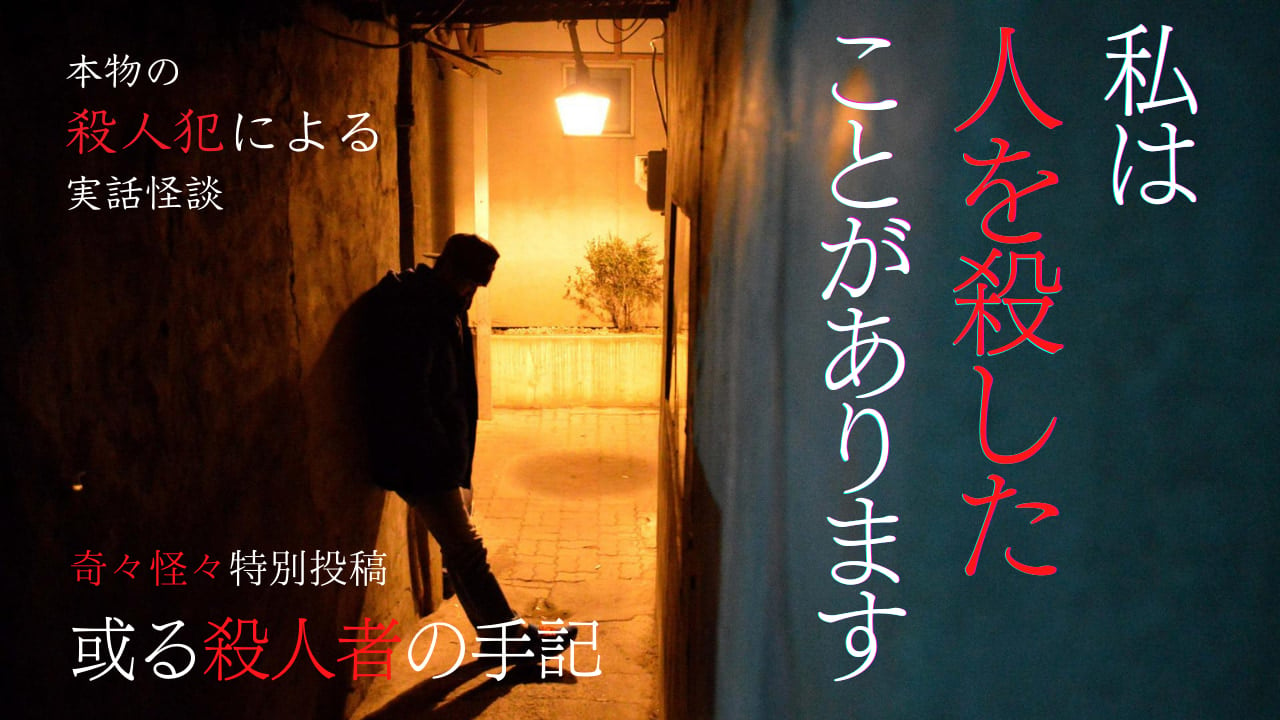





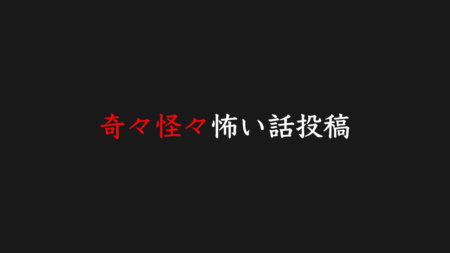





















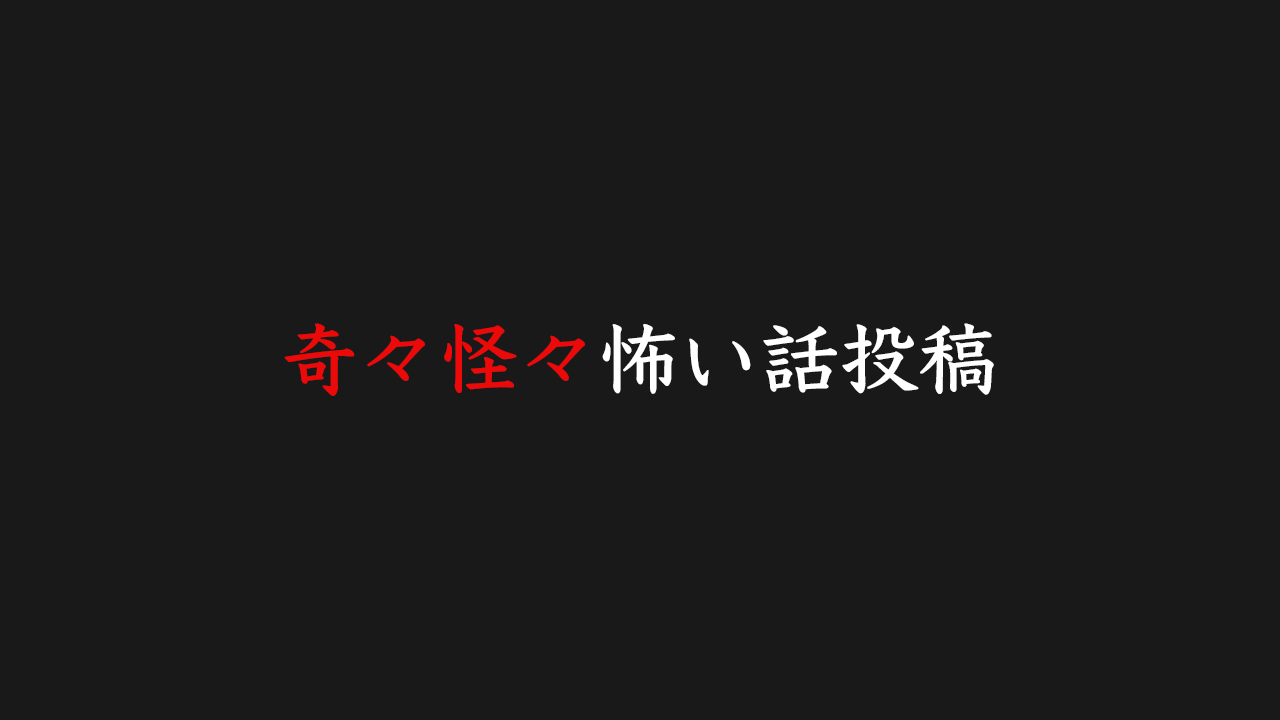






こっわこの話えぐい、やばくね?
百物語は、絶対にしてはいけないと言われてますよね。前、大学のサークル?でふざけてやっていた人が、急に心臓が痛いと言い出し、調べた結果、発作で亡くなったそうです・・・