するとミコが揺れる木々を見上げて呟つぶやいた。
「やっぱりね」
「やっぱり?」
そう返す俺に彼女はこちらをじっと見て答える。
「あなたが招かれざる客ってことよ」
〇
小学生の頃に何度か親に連れてきてもらったくらいで記憶になかったのだが、境内は思いのほか広い。見上げても木々が視界をほとんど遮っており、空が狭い。鎮守の森というのはまさにこういう神社のことを言うのだろう。
「深山君・・・だっけ、確か新井のおじいさんとこで働いてるよね」
「え、なんでそれを」
「だって私、あそこの骨董屋よく行くから」
歩きながら平然と答えるミコに俺は首を傾かしげる。街中にただ一つの骨董品店とはいえ、客足もそこまで頻繁ではなく、たまに来るのはじいさんか、ばあさんか、あるいは自分のような好事家くらいだ。まかり間違っても女子高生が来たところなど、見たことがない。訝しんでいる俺に気付いたのかミコが言う。
「あ、行くって言っても別に店ン中うろうろしたりしないの。新井のおじいさんから預かりものを受け取るだけ」
道理で見たこともないわけだ。骨董品店といっても買取やら会計、仕入れなんかはお金が絡むし、学生風情にはまだ早いと言って全て店主が取り仕切っている。もっとも俺が学生でなくなる頃まで、あの骨董屋が続いているかは定かでないが。そんなことで店主が趣味で全国津々浦々、時には外国から買い集めてきたという蒐集品、もといガラクタを整理整頓するのが俺の主な仕事だった。ミコはきっと、その様子をたまたま見かけたのだろう。
ああそうかと一人で納得していると、ミコが言う。
「あのね、気づいているかもしれないけど、深山君には今、良くないものが憑いている」
心当たりはあったが、そう直接的に言われてしまうと少々面食らってしまう。何よりここが神社ということもあってか、余計に不気味な感じがした。
「さっきのやっぱりって、そのことだったんだな・・・」
ミコはうなずいた。
「そう。まあ、何も言わずにここまで来てくれたんだし、君もなにか感じるものはあったんでしょ?」
































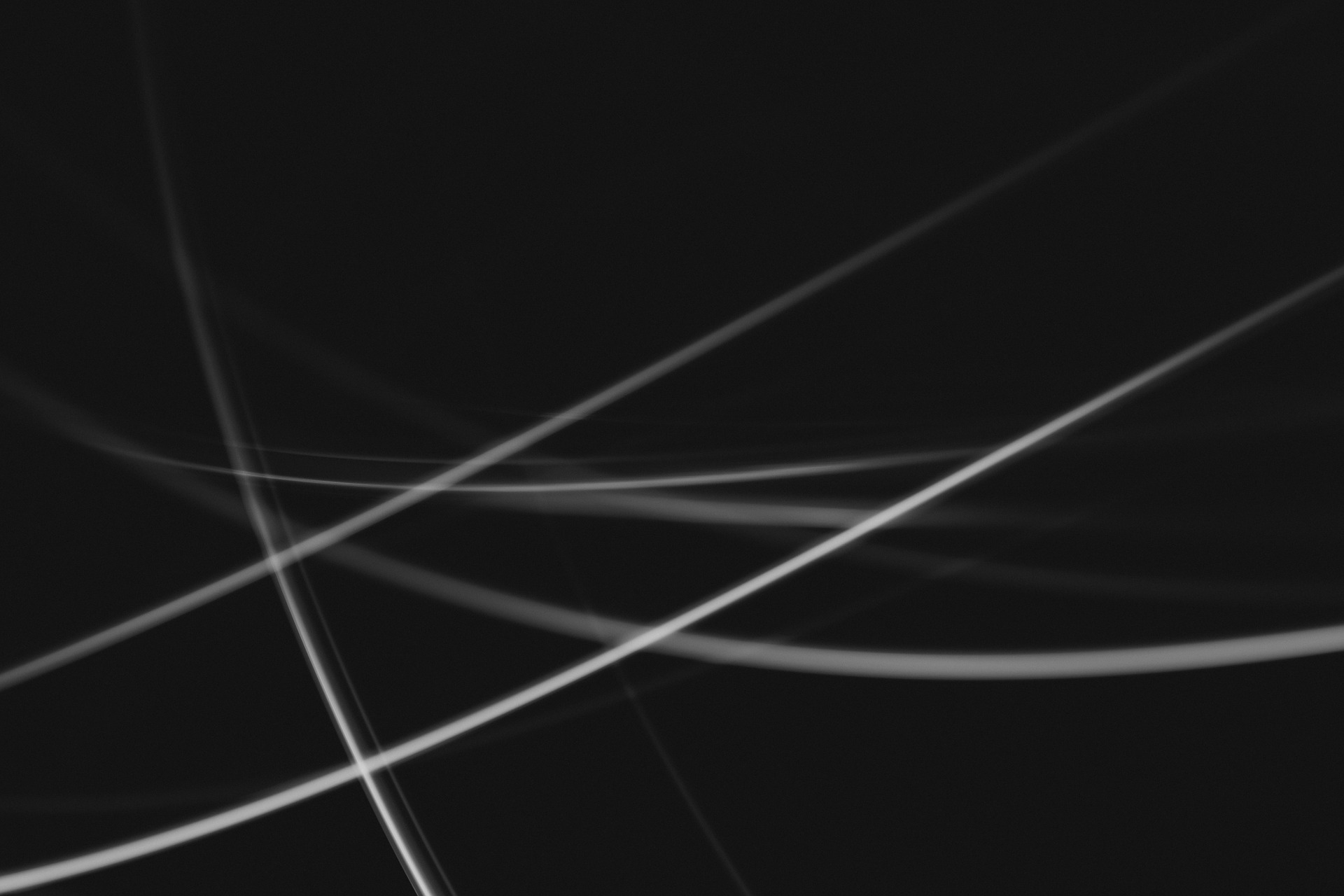







※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。