皆さん、「男尊女卑」って言葉、ご存知ですよね。
多くの場合、悪い意味で使われる言葉です。でも、私の祖母の使い方は違いました、「女の方が優れてる」的な意味合いで使ってたんです。これは、そんな祖母から聞いたお話です。
祖母が生まれたのは、山間の農村。
戦争の被害は比較的少なかったものの、戦後まもなく過疎化し、今では地名すら残ってない。そんな地域だったそうです。
村の外れには大きな池があり、村の人間は子供の頃から「あの池には神様がいる」と教えられて育ちます。
その神様は村の守り神であり、村人以外は近づいてはならない。
神様は女性で、女が近づくと機嫌を損ねる。
だから、池に近づくことができるのも、神様の名前を知ることができるのも、呼ぶことができるのも、すべて村の男だけ。
故に村では、神様に近づくことの出来る男を立て、女たちは、その男達の世話をする事で信仰を示していたんです。
村では年に二回、春と秋に神様を讃える祭りが開催され、その日になると男達は村の全てを女に任せて、1日中池の周りで祭事を執り行います。
普段の祭りは、神様に感謝を捧げ、讃えるもの。
しかし、春の祭りで「お告げ」が下ると、秋の祭りで「お告げで選ばれた男」が池の神様に捧げられる、つまり「生贄」の儀式も兼ねていました。
この祭事には、男には知らされない、代々女だけに口伝で伝えられている話があります。
池を囲む森の手前、女性でも立ち入る事が許された場所にある小さな社。その社の管理は女の仕事でしたが、実は神様は普段はそこに居るのだと。
神様は女を嫌っているわけではなく、寧ろ友好的で、伴侶を求めているのだと。
池は神様にとって「寝所」にあたり、故に男以外が近づく事を嫌うのだと。
そして、池の神様に捧げられる。つまり、伴侶として選ばれる男は、村の中で「役立たず」と見なされた者だけである、と。
働かず、家ではふんぞり返り、飲み食いするだけ。借金を作る、暴力をふるう、家族を苦しめる男。
村の女たちは毎年、男が居なくなる祭の日に集まり、排除すべき「役立たず」つまり「生贄」が居るのかを話し合います。
排除すると決めた者の名を、紙に書いて社に奉納する。すると、神様がその男を自らの伴侶に選び、「間引いて」くれる。
この村で女が使う「男尊女卑」の言葉は、本来の意味でありません。
男の価値は「生贄に選ばれない事」であり、家庭を、つまり女を大切にしてくれる人にこそあります。
「男は神に近づける、だから自分は偉いんだ」と思い込んでいる男性を陰で、「女が男の命を握ってるのに」と、馬鹿にする。そんな言葉として使われていたそうです。
祖母は、そんな村で生まれました。
でも、物心つく頃には、過疎化した村で暮らす事が難しく、祖母一家は村の外に引っ越したそうです。
私がこの話を聞いたのは、会社の上司の愚痴を祖母にこぼした時でした。
その上司は、典型的な男尊女卑の考えを持つ人でした。
「女は男を立てるべき」
「男に従うのが当然」
そんなことを平然と言う人で、私はうんざりしていたんです。
すると祖母は笑って、こう言いました。
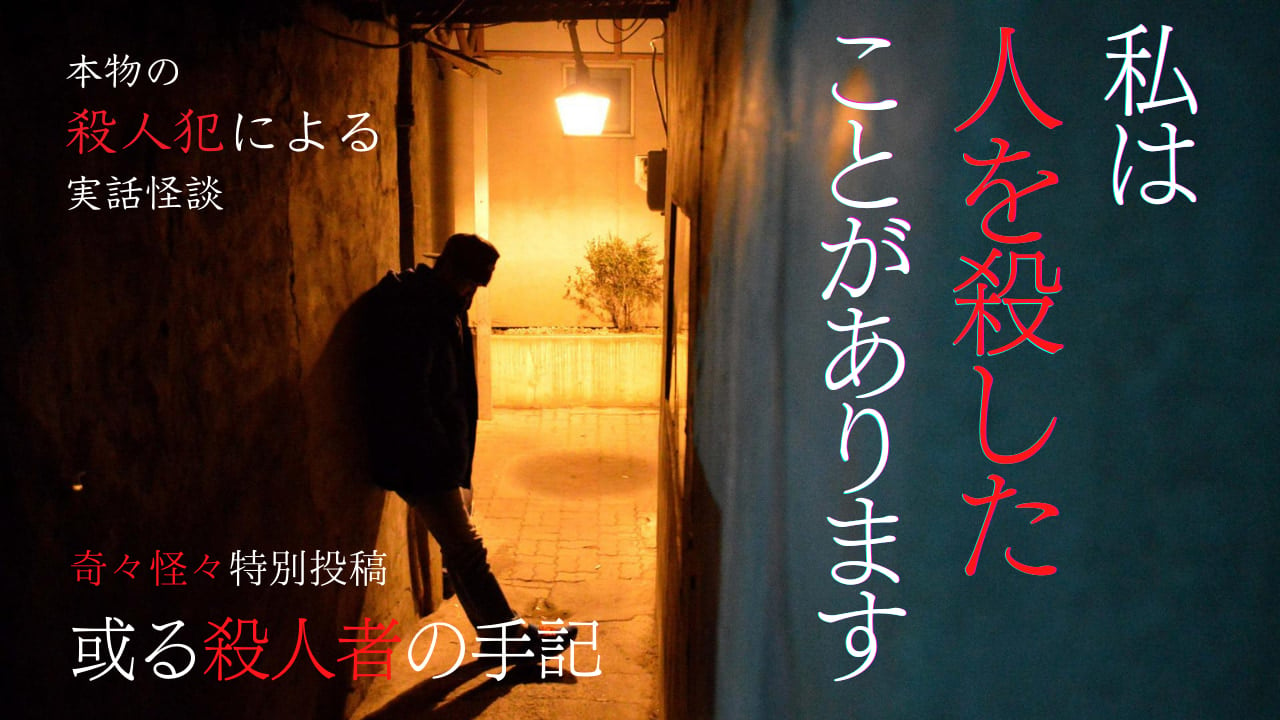

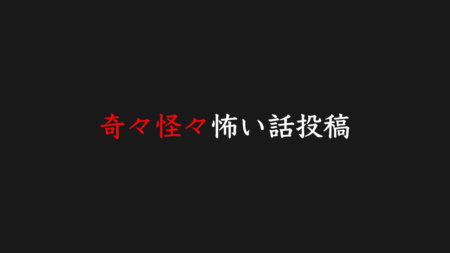





































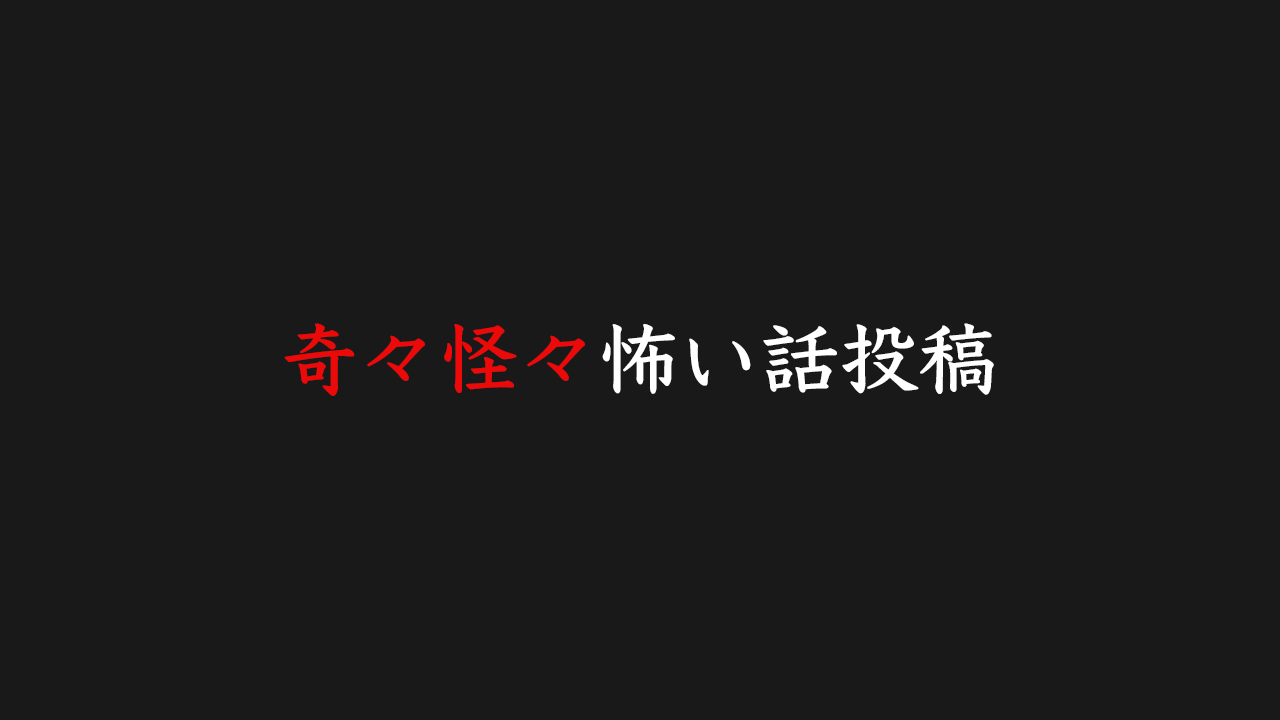


知れっと祖父と父が排除されてるやん
いいね。面白い。
このお話の女性の旦那はどうなるんだろうね
村の守り神なんだから主人公の身内ではない会社の上司にまで及ぶんだろうか? 一般的な男尊女卑な考えの持ち主なだけで役立たずな人物なのかも分からないし。