高校に入ってからとある骨董品店でアルバイトを始めたのだが、どうも最近様子がおかしい。昨日まであった物が消えたり、物陰から視線を感じるなんていうのはざらで(古い店だし、そんなことはまあよくあることかな)などと考えていた。しかし、店内を整理しているときに不気味だなと感じた品々が、気づいた時にはカバンの中に入っているなんてことが起き始め、それが単なる気のせいではなく、明らかな異常として、目の前に現れ始めたのだと自覚するきっかけになった。
この怪異に心当たりがないと言えば嘘になる。あれは、二週間ほど前のことだった。その店は新井という老人が店主をしている。気さくだが、いかにもな昭和親父でちょっと面倒くさい。年齢は不詳。六十歳にも見える時もあれば、九十歳に見える時もあった。だいたい一日中、奥にあるレジの椅子に腰かけて古文書のようなものを読んでは「お!」とか「あ!」とか声をあげているのだが、用があるときに限ってどこにもいない。大方、近所に買取か散歩でも行っているんだろうが、なにせタイミングが悪い。
その日も、店の外にある倉庫内のガラクタ整理を命じられたいたのだが、何を基準に捨てたらよいのか、何を基準に店内に移動させれば良いのかを聞こうとしたときには、すでに行方知れずだった。とりあえず、ジャンルごとに分けて、倉庫内に仕舞い直していこうと思った。とはいえ、あまりに損傷がひどく、とてもじゃないが売り物にならないなと思ったものは捨てていくことにした。中でもひどかったのがボロボロに朽ち果てた熊手だ。熊手の要でもある持ち手と長い爪が折れて真ん中の繋ぎ合わせの部分だけが残されている。唯一残されたその部分でさえ、虫食いでところどこと穴が空いていた。ほとんど消えかかった達筆な文字で『月宮 酉の市(とりのいち)』と書かれていなかったら、それが熊手とはわからなかっただろう。
「こりゃどう見ても廃棄だなぁ」と思わず独り言が出てしまう。新井のじいさんもまあ納得してくれるに違いない。俺はその熊手をゴミ捨て場行きの荷車の中へ放り投げた。
異変が起きたのはそれから間もなくのことであった。あくる日、教室に着いてカバンから教科書を取り出そうとしたとき、奥の方で鈍く光るものが目についた。昨日、倉庫の中で見つけた銅色の鈴だ。なぜだかわからないがちょっと不気味な感じがして、倉庫の奥の方へ仕舞しまったはず・・・。もしかすると服か何かに引っかかっていて、カバンの中に誤って入ってしまったのかもしれない。そう思っていたのだが、異変はそれだけに留まらなかった。
次に出勤した時、店に入るなり、店主が嬉々として俺にあるものを見せてきた。それは幕の内弁当くらいのサイズはあるであろう硯(すずり)だった。
「見よ少年、こんなものォ博物館でも置いてないぞ!」
硯なんて小さけりゃ小さいほど持ち運びやすくて墨汁を使う量も少なくて済むというのに、まるで巨人が使うために造られたみたいだった。それを店主に伝えると「カッカッカッ!」とどこぞの悪代官のような笑い声を出して、店の奥へと消えていった。問題はそのあとだ。仕事を終えて、くたくたになって家に帰ると、なんと自室の机の上にあの馬鹿でかい硯が置かれているではないか。俺は愕然とした。あのあと硯は間違いなく、土埃の香りがするじいさんお気に入りの和室へ運んだのだから。ただでさえ、その日は腰を言わした店主に代わって大量に重いものを持ち運びしたので正直、恐怖よりもいらだちが勝った。だが、このどうしようもない現象に俺はただため息をつくことしかできなかった。
普通の人であれば、そんなことが続くような店はとっとと辞めてしまうのだろう。だが、オカルト好きが高じて、好き好んで骨董屋なんかで働いている自分には願ったり叶ったりなことで、良くないことなんだろうなと心のどこかで思ってはいたものの依然、辞められずにいた。そんなあるとき、学校で妙な噂を耳にした。
なんでも占い研究部で黒魔術の真似事をしていた女子たちが、手順を誤ったのか集団パニックになってしまったのだという。それをたった一人、指を鳴らすみたいに事態を丸く収めた女生徒がいる―――――というのがその噂の真髄だった。
無論、それが今、俺に声をかけてきたこの女生徒だと知るのはもう少し先の話になる。三限目の授業が終わってトイレにでも行こうかと廊下を歩いていた時のことだった。長い黒髪に切れ長の目をしたその女生徒は、こちらを真っすぐ見つめながら、俺の目の前に立ちはだかった。心の奥底まで見通すかのような黒く澄んだ瞳をしていた。
「きみ、このままだと死ぬよ」
廊下に響き渡るざわめきが一瞬にしてかき消される。何を言われたのか理解できなかった。返事もできずに呆気にとられている俺をよそにその少女は続ける。
「なぜ、あなたはそこにいるの?」
俺を見ているようで見ていない。目の焦点が合わないのだ。しかし、その眼差しは一層鋭さを増し、射竦められるかのようにして俺は固まっていた。実際はものの数秒のことだったのだろうが、それはとてもとても長く感じられた。しかし、不思議と苦痛ではなかった。
































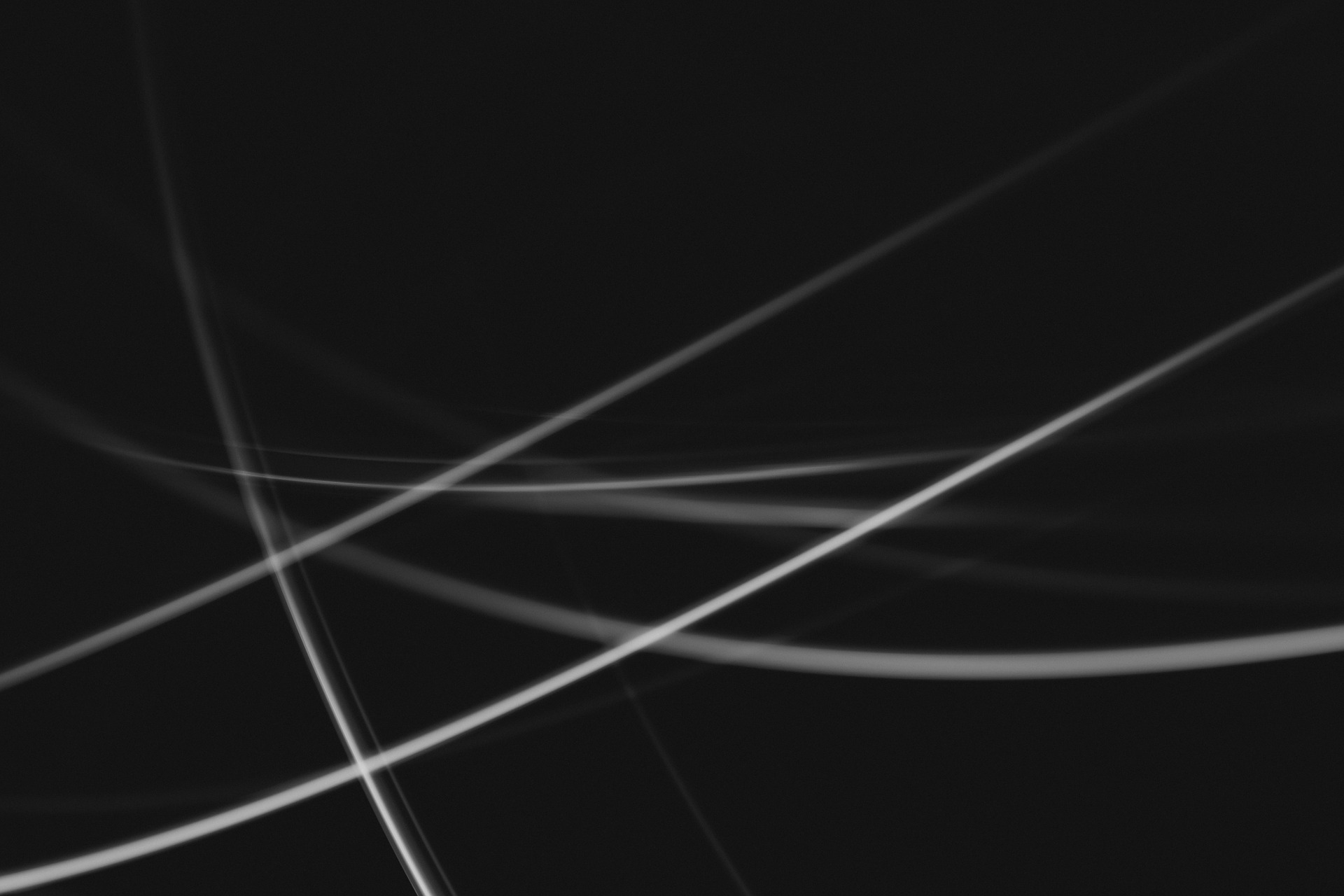







※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。