月の逆光を浴びた人影がカーテン越しに浮かんでいた。
「ひいっ…」
情けないが喉が狭まって悲鳴があまりでなかった。
俺は布団に潜り込んでガタガタと震えた。
どうして二階の窓に人影が映るのか。
あれは人間じゃないのか。
もしかして幽霊なのでは、とか非現実な妄想を並びたてて奴がどこかに行ってくれるのを切に願っていた。
コツ、コツッ
小さくだが窓は叩かれ続けていて、俺は寒さのせいと恐怖で泣いていたせいで鼻水が垂れてきてて何度かすすっていた。
それからどれくらい時間が経ったのかわからないが、永久に続くのではと思えたコツッという音はいつの間にかおさまっていた。
布団方顔を出すと冷たい空気にあてられて頬が張り、鼻腔がツンとした。
俺はあの白装束がまだ家の近くにいるかもしれないと考え、再び窓に近づきチラっと覗くこうとしてカーテンの端を摘む。
そしてゆっくりと外を覗き込んだ。
「うわあああッ…!?」
カーテンを捲り外を覗くと、擦りおろしたようにぐちゃぐちゃな顔面を窓にへばり付かせた白装束がいた。
俺は悲鳴を上げて尻もちをついた。
俺がカーテンを手放したせいで自然と白装束は視界から消え失せる。
唖然と窓を見上げるが、月明かりがうっすらと確認できるだけで奴の人影はそこになかった。
その日、俺は一睡もせず電気をつけて毛布に包まりながら朝を待つ。
朝早く母ちゃんがトイレに起きたのに気付いてすぐに居間に降りた。
とにかく一人が怖かったのだが、部屋から出て暗い廊下や階段に白装束と鉢合わせしたらなんてネガティブな考えが先行して、どうにも部屋から出る勇気がなかった。
居間のコタツに潜り込んだ俺は次第に安心しきたのか寝入ってしまい、気が付いたら家族が全員揃っていて、年末の特番見て笑っていた。
それを見てようやく本当に安心した俺は昨夜の事を無理矢理忘れて寝正月を満喫することに決めた。
今でも実家に帰省するたびにあの白装束を思い出すことはあるが、記憶もちょこちょこ薄れていっている。
あれは人間の悪戯だったのだろうか。



























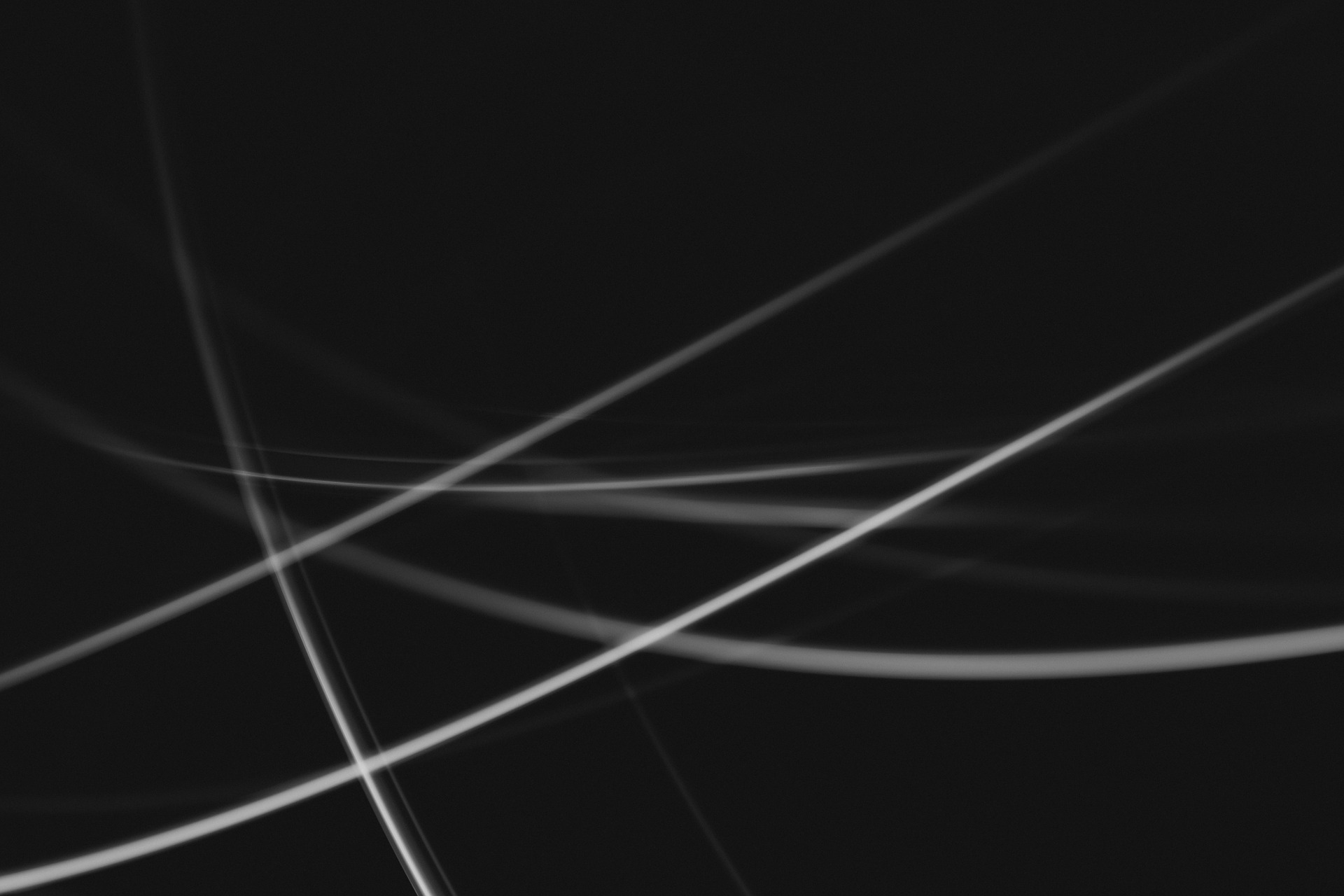













人間でも幽霊でも怖すぎる