※
シャワーを浴び、置いてあった自分の私服に着替える。外へ出ると、既に雨は上がっており、夜の帳が降りきっていた。
血生臭い匂いから解放されて、雨上がりのさらりとした心地よい空気に気分が浄化されるようだった。
もう、あの声は聞こえてこない――そして、それは金輪際聞こえてこないだろう、という確信が自分の中にあった。
電車に乗り、帰路へ就く。現代人のひしめき合う車両に紛れ込むと、やっとまともな世界に戻れた心地になる。皆退屈そうにスマホに目を落としている何時もの光景に安心した。
両手でつり革に掴まり、ぶら下がるようにして体重をかける。窓に映る自分は子供じみていたが、何処か生き生きとしていた。
ガタン、と電車が大きく揺れ、反対方向に体が引っ張られる。つり革を握る力を強め、踏みとどまった。
その拍子に。
隣に居た人の足を踏んづけた。血の付いた私のスニーカーが隣の人の靴を踏んでいる。
ぎょっとした顔で隣の男が見てくる。制服を着た高校生の男だった。
何だか途轍もなく申し訳なくなる。申し訳なさで気持ちが一杯になる。急いで足を退ける。
数秒間、目が合ったまま、沈黙が流れた。この子はきっとあの言葉を待っているに違いない。
そうだ。早く。早く言わないと。
早く――。
前のページ
5/5
この話は怖かったですか?
怖いに投票する 19票

























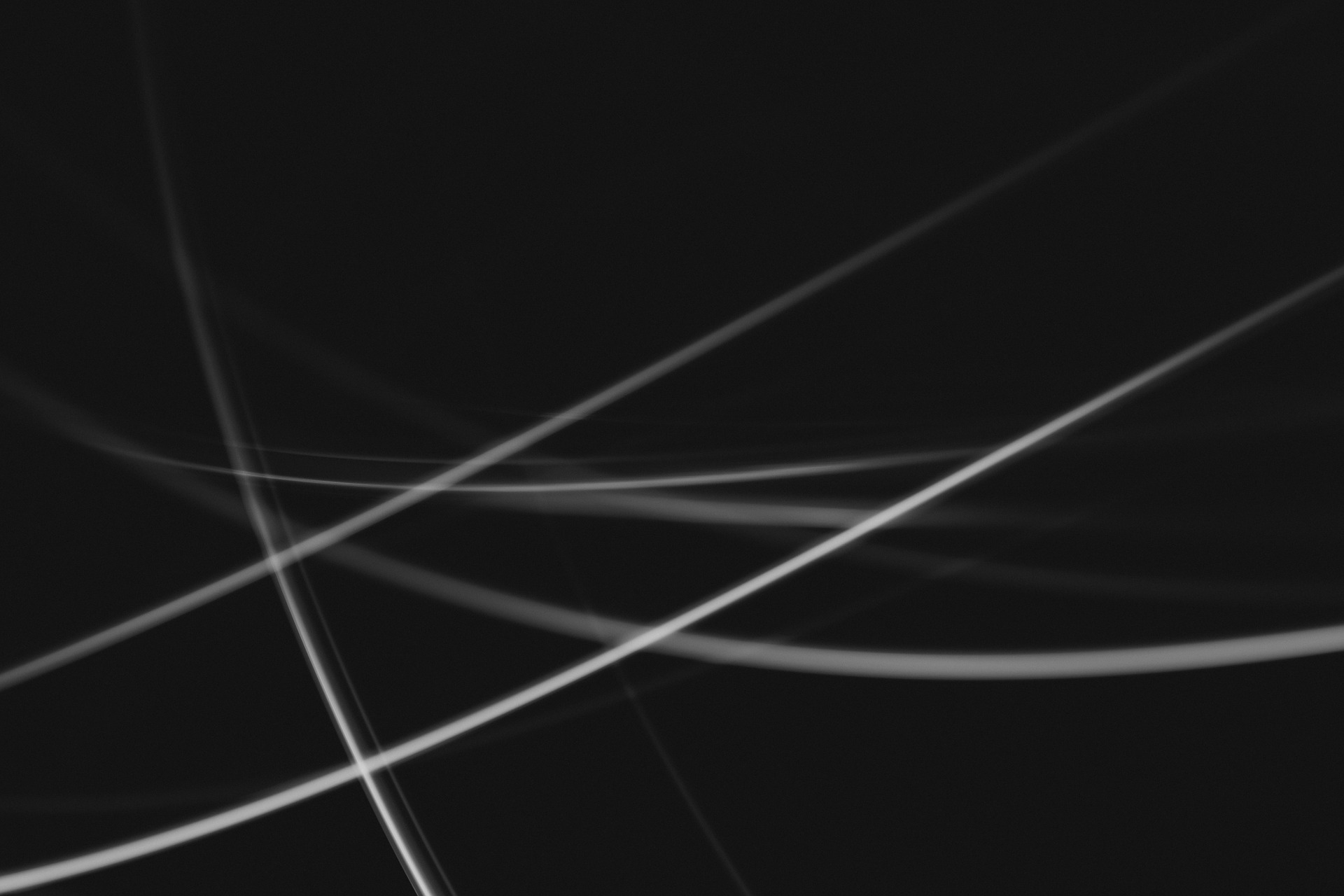








※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。