が、コール音ばかりで一向に出る気配がない。
このまま留守電に繋がるかと諦めかけた時、ようやく通話が繋がった。
「カズキ!俺だけどお前大丈夫だったか?」
『ああ‥‥‥』
やけに力無く気の抜けた返事をしてきた。
ただの溜息のようにも聞こえる。
「お前の周りで変なこと無かったか?」
『……何で俺だけ』
「はぁ?おい、今どこだよ?」
『早く帰りたい』
質問に答えず脈絡の無い事を呟き、そこで通話は切れてしまった。再度発信したが今度こそもう繋がらない。不穏な空気を感じ取り、念の為カズキの自宅に連絡してみるとやはり危惧した通り「まだ帰ってなくて心配している」と電話口に出た母親が言った。首筋を嫌な汗が伝う。
明らかに尋常じゃない。何かヤバいことが今あいつの身に起きている。
そう確信した時、赤い手の家での一場面が唐突に脳裏に鮮明に甦った。
あいつあの部屋で自分の手を壁の手形に重ね合わせていた。多分きっとアレは絶対やってはいけない禁忌だったに違いない。それであいつはおかしくなり行方をくらましたんだ。
まだ間に合うか?頼む、無事でいてくれ。
そう切に願い、一刻を争う事態に俺は再び赤い手の家へ向かおうと腹を括った。あの廃屋に囚われている可能性が高い。
もちろん単独じゃなく警察に事情を話して複数人で行くのが賢明だ。
羽交い締めにしてでも連れ戻さないと。
まず必要な物を取りに急いで廊下に出て自分の部屋へ向かい、ドアを開け部屋の照明のスイッチを入れた。
電気コードで首を吊ったカズキが目の前にぶら下がっていた。
既に時間が経っているようで足下に糞尿を垂れ流し、全身に赤い手形が付いている。
脳が現実を認識するのを拒否していたがそれも束の間、理解が否応無しに徐々に追いついてきた。
……あの変な足音、お前だったのか。
そういえば玄関の鍵掛けて無かったな。
何だよ、それ。
全ての気力を失いその場で床にへたり込み、微かに揺れている紫の顔のカズキを、涙に滲む視界でぼんやり見上げた。
あの時、カズキだと気づけていれば少なくとも命は救えたかもしれない。
もしかして俺は試されていたのか?
勇気を出して、廊下を確認できるかを。
フフフッ、と心底楽しそうな女の笑い声が聞こえた。































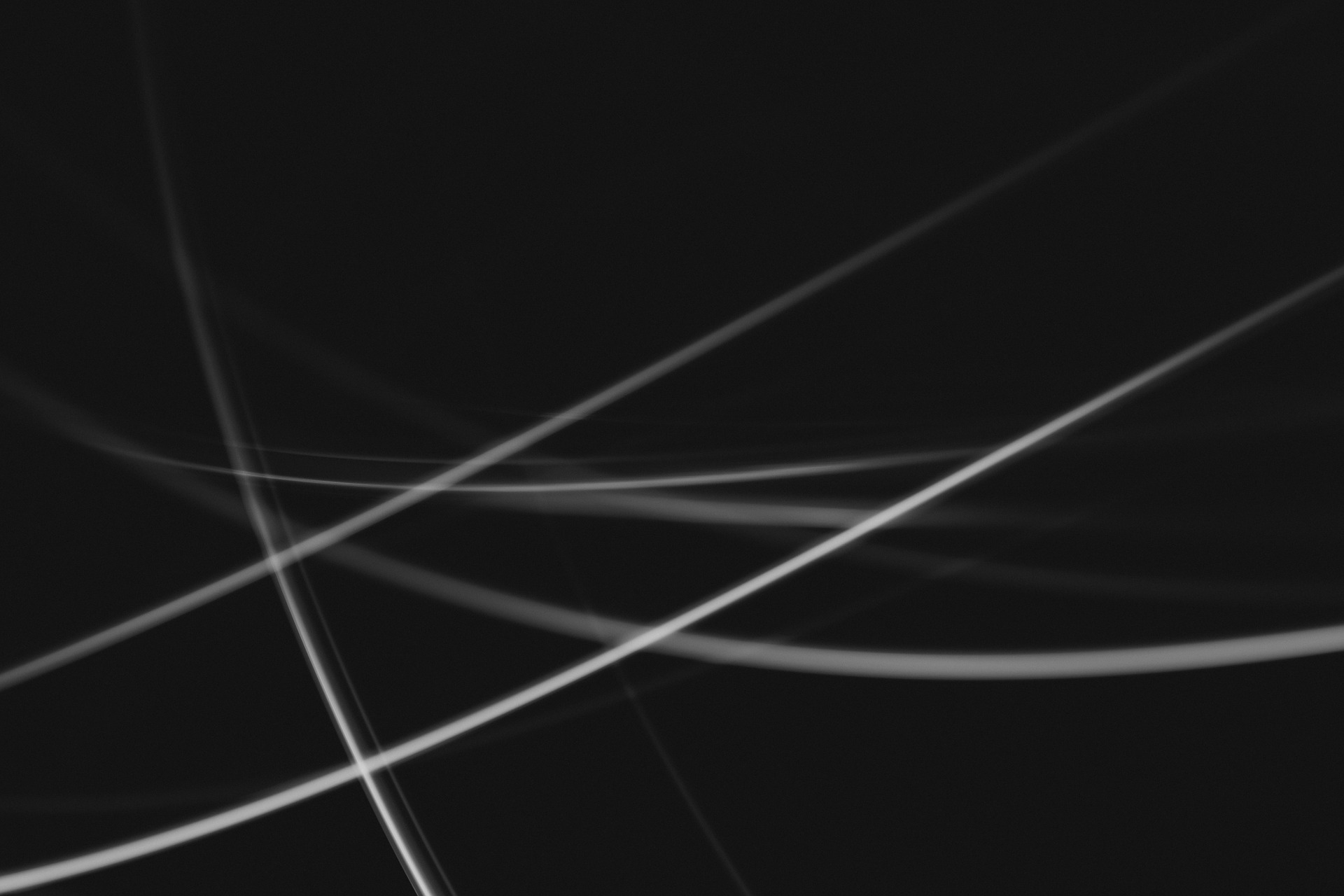









こわ