※
「それは、相当きめえな」
向かいに座る男――真人は口にホットサンドを運ぶのを中断し、私を見据えた。その表情は、心配半分面白がっているの半分といったところだった。
「でしょ」
私はため息交じりに言う。
昨夜の体験は私にとって、まあまあ厭なものだった。トラウマという程ではないにしろ、恋人に愚痴るくらいの出来事ではあった。
「でもさ、本当に謝ってただけなの? 例えば、その後ついてきたとかさ」
「多分、ついてきてはない。うん。私、一応電車降りて、そいつがついてこないの確認したんだけど、降りては来なかったから」
「なら、大丈夫か。単純に変な奴だったんだな」
真人はホットサンドを豪快に頬張った。小気味の良いサクっという音がして、間に挟まれたチーズが少しだけはみ出す。品がある食べ方とは言えないが、美味しそうに食べるなあ、と思う。
触発されるように、パスタをフォークに巻き付けて、口に入れた。
「でもさ」
真人は少し真剣な顔つきになっていた。
「ん?」
「やっぱ気持ちわりいよ」
「だよね」
「アヤハラだね」
「アヤハラ?」
「謝るハラスメント」
何それ、と思わず噴き出した。真人の顔も合わせるように破顔する。
「語呂悪いよ」
それで言うとスメハラの方がひどかったよ、と付け足す。
その瞬間だった。
――ごめんなさいね。
まるで昨夜の再現のように、全く同じ距離感、全く同じ声色で、男の声が聞こえてきた。驚いて辺りを見渡すが、近くに居ないのは勿論、視界内にはそれらしき人影はなかった。
「どうしたん?」
「え、いや…真人、今なんか言った?」
「いや…言ってないけど」
幻聴だろうか、それにしては、やけにはっきりとしていたような気がする。私は気を紛らわせるように、パスタを舌に乗せた。
※
























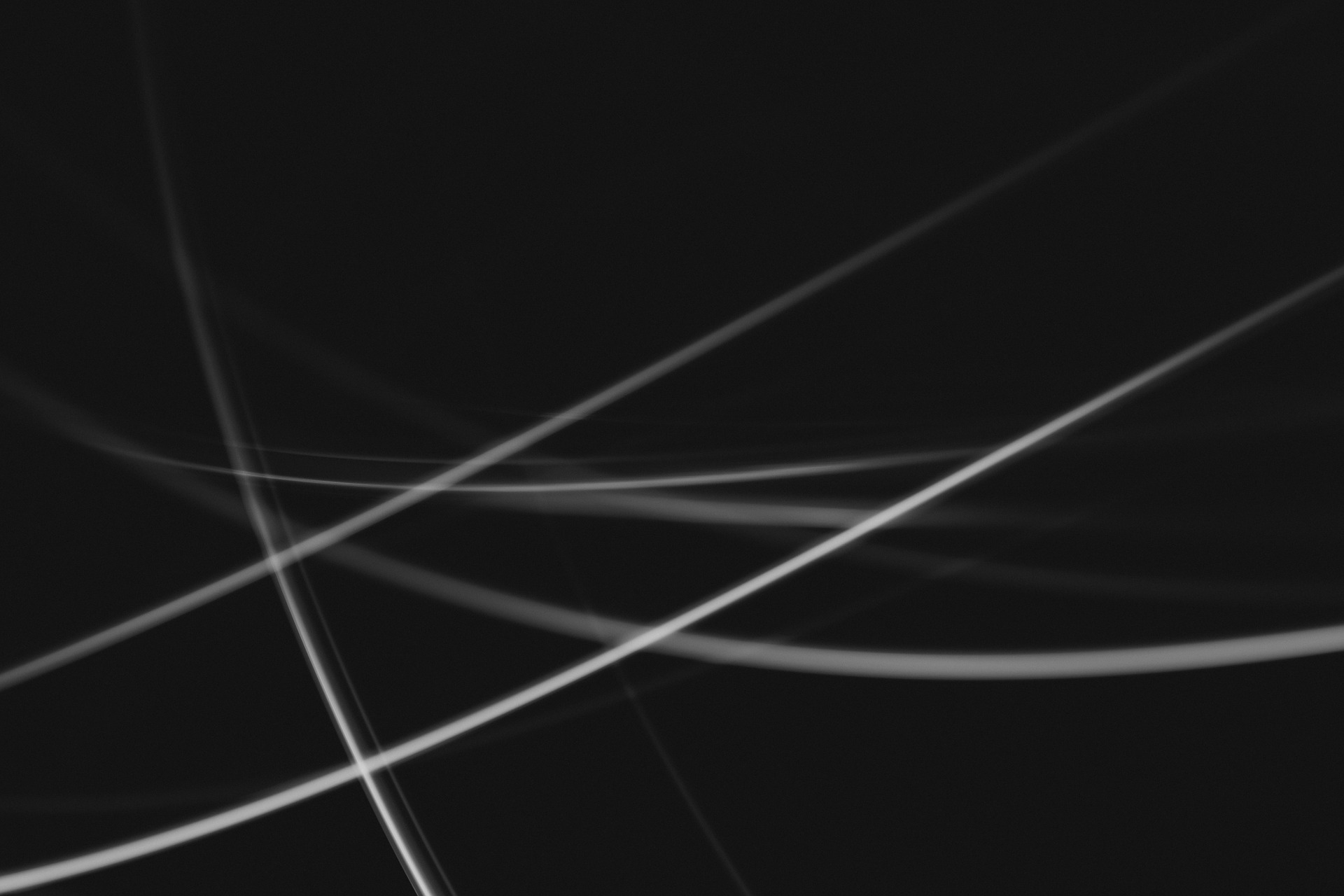








※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。