◆ 土地が刻む “見えない歴史” とは? ――○○公園周辺の静かなる侵食。
○○区○○の住宅街を歩くと、突然視界が開ける。フェンスに囲まれた広大な空き地が、不自然な断絶を作り出している。
スマートフォンの地図アプリはここを「○○公園予定地」と表示するが、区の公式サイトには「2075年完成予定」の文字が淡々と並ぶ。
「あの土地の面積が、少しずつ広がっているんですよ」
近隣住民はそう証言する。地権者の多くが「公図と現況が合わない」と区に相談するが、区の測量では「誤差なし」と判断される。しかし不思議なことに、訪れる人によって土地の広さの認識が異なるという。
地元の人間ほど「違和感」を報告する割合が高く、部外者には全く感じられないが、近年では区外からの訪問者の間でも「何か変」と感じる人が増えつつある。
「境界標が動いたんです」
土地家屋調査士のT氏は、皺くちゃになった測量図を広げた。
2018年秋、未買収地隣接の民家で実施した境界確定測量で、登記簿と17センチの誤差を発見。再測量を試みた翌日、近隣5軒のブロック塀が一斉に位置変更されていたという。
測量図の隅には、赤インクで「参照:特殊地域維持管理要領」と走り書きされていた。
「ここだけは墨塗り文書のまま残っていまして…」
区役所本庁舎の明かりが消える午後10時、建築指導課の若手職員は書庫の奥から分厚いファイルを引き出した。
「昭和時代地区対応要領」と表書きされた非公式マニュアルには、戦後のGHQ検閲印が押されていた。
匿名を条件に語る職員が指差すのは、コンクリート配合基準の項。
「セメント1tに対し竹繊維3.3kg」との記載が、かすかな筆跡で追記されていた。
2015年の耐震改修工事で、この数値を適用した物件だけが、異なる経年変化を示すことが後に判明している。
「昭和19年の資料を調べるうち、この数字の一致に気が付きましてね」
相続登記の専門家であるK氏が戸惑ったのは、2017年に扱った土地の謎めいた沿革欄だった。
平成の地目変更記録の下に、かすかに「昭19.10 軍事用地」の文字が浮かび上がっていた。
彼女が区史編纂室で発見したのは、1944年の土地管理台帳。現代の登記システムに登録された地権者IDの下4桁が、当時の罹災証明書番号と完全一致していた。
区域内の古い寺院の過去帳には、1944年10月の欄に「終止符」と記された空白ページが存在する。住職によれば、先代から「このページだけは決して埋めるな」と言い伝えられているという。
「進捗率維持が最重要事項」
ある郷土史家がリークした区の内部資料には、そう記されていた。
それは「特殊地域維持率33.3%」という数値とともに、年に一度、特定日に実施される「区域調査」の記録だった。
添付された地図には、都内23区に散在する132カ所の「公園予定地」が赤丸で囲まれている。それらはどこも数十年来、着工されることなく放置されたままだ。
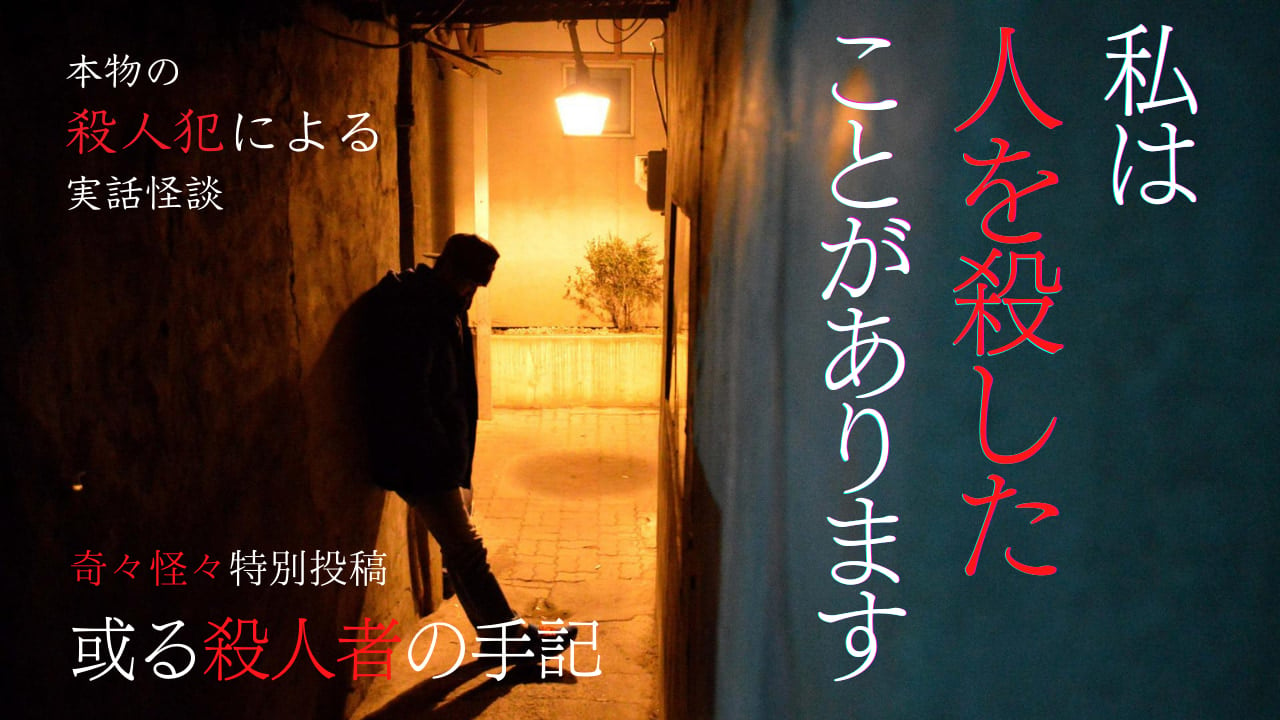


























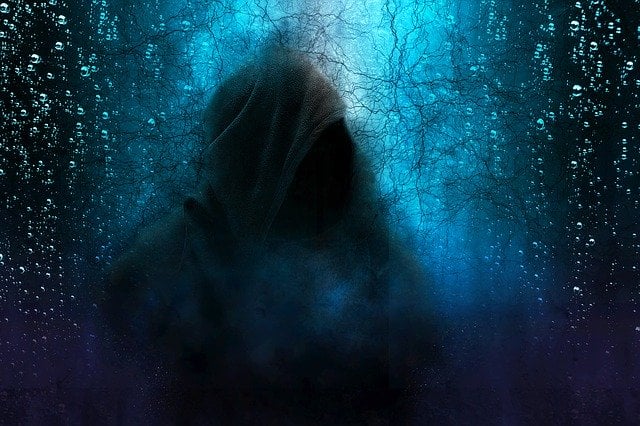









※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。