・・・ある日の昼下がり
アタシは鍋の具材と土鍋を詰め込んだリュックを背負い、彼の部屋に入った。
入室にあたり、別に犯罪じみたことはしていない。
このあたりは田舎なので、
アパート内に住む老いた大家さんに
「アタシ、彼の婚約者なんです」
などと言うと、たいていは鍵を開けてくれるのだ。
そして今回も、その例に漏れなかった。
アタシは玄関で丁寧に靴を脱ぎ、部屋にお邪魔する。
・・・そして釣りで使わなかった、もう片方のスニーカーを玄関に置かせてもらった。
片方は獲物らに踏ませ、もう片方はアタシの料理を見守ってもらう。
両方にちゃんと役割を与えてあげるのもアタシのこだわり。
さて、彼が帰る前に、美味しいおでんを作らなくちゃ!
この料理は自分のためだけど、
だからといって、いや、だからこそ、味で妥協はしたくない・・・
したくないんだ・・・
・・・そしてアタシは作った。
納得の一品を。
満足したアタシは調理器具を洗い、撤収に取り掛かった。
鍋は置いてくのかって?迷惑賃がわりだわ。くれてやる。
部屋を出る間際、テーブルの上におでんの鍋を置いた時、妙な手紙を見つけた。
色々な大学の合気道部宛の寄稿文だ。
「・・・あなたも 良い趣味を持っているようね・・・」
女はニタリと笑い、部屋を出て行った。
女はすっかり愉快になったのだろう。
玄関に置いていた片方だけのスニーカーを拾うことをうっかり忘れてしまったのだから・・・
・・・男の部屋を出たあと、女は自宅の鍵がポケットにないことに気付いた。
男の部屋では無い。出る前に証拠を残さぬよう、髪の毛一本も残さず回収してきたのだから。
「となれば・・・あの廃墟ホテルね・・・」
すでに日も傾いているし、廃墟に着く頃には暗くなっているだろう。正直怖いが、家の鍵がそこにある可能性が高い以上そうも言っていられない。
やむなく女は廃墟に向かう。
・・・着いたときには案の定、周囲は真っ暗。
廃墟の雰囲気も不気味さが増して昼間とはまるで別物だ。
それに昼間は趣味ブーストがかかっていたから恐怖感も少し麻痺していた。
しかしいまは忘れ物を取りに来ざるを得ない否応なしの状況のためシラフである。
ともあれ、仕方なく女は携帯のライトで足元を照らしつつ、恐る恐る廃墟の中へ入っていくほかなかった。
昼間では、2階の窓辺から峠の道路を観察していた。
おそらくその辺りに鍵は落ちているだろう。
記憶を頼りに、すぐに2階へあがる階段を見つけた。
そして、まさに最初の一歩を階段に乗せたときだった・・・
「ヴォォォォォォォ!!!!」
突如、獣のような咆哮と、床を激しく踏み込んだような大きな足音が廃墟中に響き渡った。
「ひぃ!!」
女は思わず、悲鳴をあげた。
すると、雄叫びはピタリと止まった。
急にあたりは元の静寂に包まれる。
な、なんだいまのは。
得体の知れない何かがこの廃墟にいる・・・
女は呼吸を止めて、周囲に意識を集中した。
ひたっ・・ひたっ・・ひたっ・・・
来ている。
なにかの足音が、こちらに近づいて来ている・・・
間違いなく、先ほど咆哮をあげたやつに違いない。
女は血が凍る思いがして、2階へと駆け上がった。
鍵を!はやく鍵を見つけないと!!
2階に着くと、すぐに階段脇の部屋に入った。
昼間に自分が入った部屋のはずだ。
窓辺へと近づいてライトで周囲を照らす。
すると、ちょうど昼間に自分が道路を観察していた辺りの床に鍵は落ちていた。
女はすぐさま鍵を拾い上げ、部屋の出口のほうへ振り返った。
・・・全身が総毛立った。
身の丈は六尺七寸(約2m)を超えるであろう、道着に袴姿の大男が部屋の扉の前に仁王立ちしていた。
時が止まったかのように、一瞬の沈黙が流れた。
が、男はグニャリと歓喜の表情を浮かべ、
そして大口を開いて・・・
「センパイ イタァァァァァ!!」
ゲヒャゲヒャ笑いながら女に駆け寄ってくる。
「いやぁぁぁぁぁぁ!!!」
女は張り裂けるような悲鳴をあげて逃げまどう。
運良く男の横をすり抜けて扉の前に来ることができた。
廊下に出て、すぐに階段を駆け降りる。
が、残酷にも後ろから
ダンッダンッダンッ
と男が追跡してくる音が聞こえる。
恐ろしい。
女は男がどこまで迫っているのか不安に駆られた。
そして、つい後ろを振り返った瞬間、女はあと地上まで数段というところで、階段から足を踏み外してしまった。
女は踊り場に身体を強く打ちつけられた。
すぐに身体を起こそうとするが、全身に激痛が走り、思うようにいかない。
逃げないと・・・逃げないと・・・


























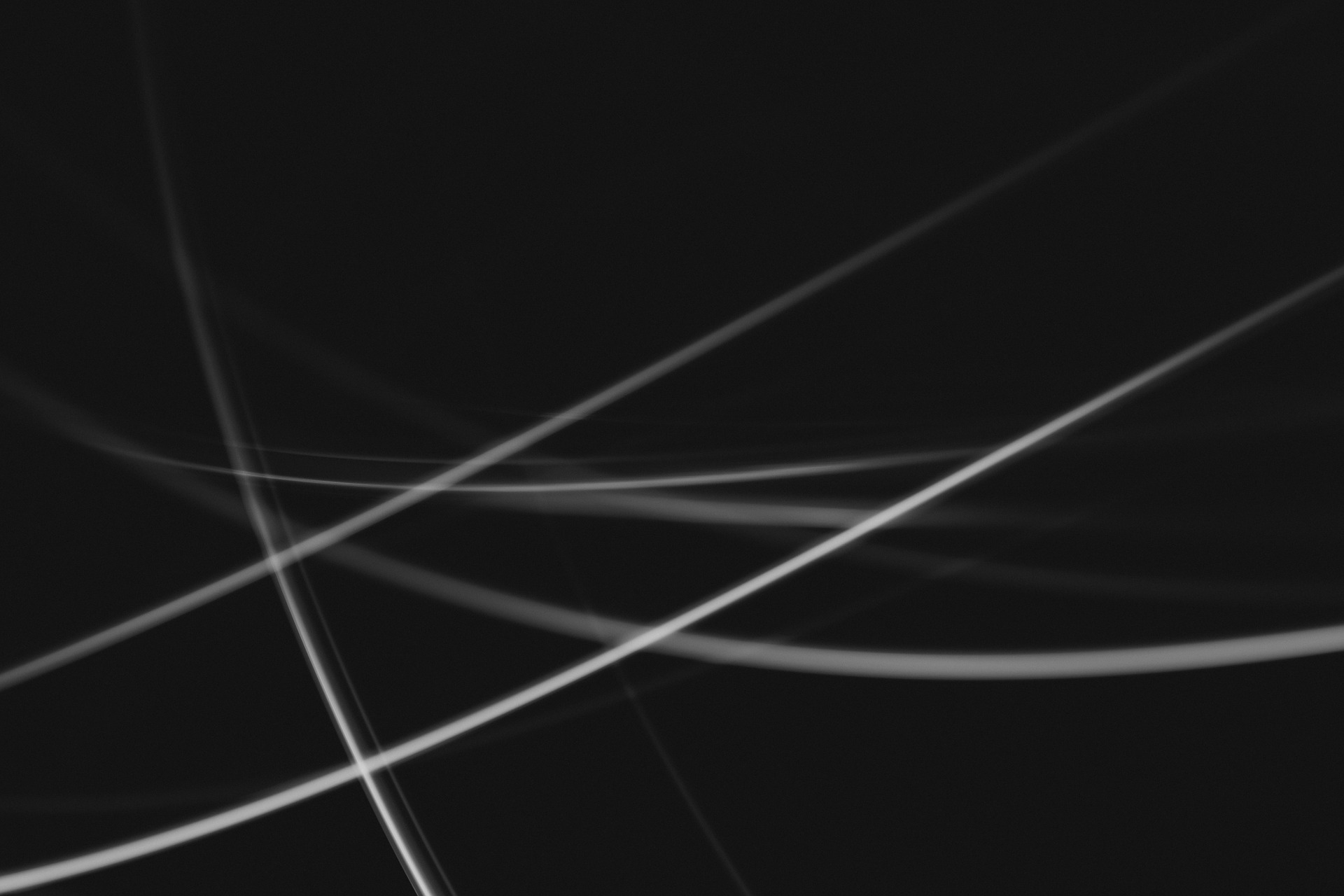








何だか最後までわからない話ですね。