ガシッ!
「いたいっ!」
詠里はジャックのヘタを問答無用で思い切り掴んだ。
「さぁ、とっとと行くわよ!!」
「先が思いやられるな」
「らしいと言えばらしいではございませんか」
詠里(片手にジャック)を先頭に、朔羅、火夜、政宗は廃墟へと入っていった。
そして、五人が廃墟に行ってから30分後。
「本当に先に行ったんだなあいつら」
コンビニの袋を持った黒は廃墟を見上げる。
隣にいた麻己音は詠里にメールを打つため、携帯を取り出した。
「今から入るって連絡入れておくか。霊が怖いとか言ってらんれねぇな」
自分の持っているコンビニの袋をチラッと見る。
「タイムリミットはかき氷が溶けるまでだな」
「溶けるまでにあいつらに渡さねぇと。つか、アイスの方が先に溶けんだろ」
「暑いと思って全員分×2のアイス買わなきゃ良かった。まさか先に行くなんて」
「メールに気づいたのが買い終わってからとか、完全後の祭りじゃねぇか。俺の分寄越せ。食べ歩きする」
「お前はどれだよ」
「ジャ○アン○コーン」
麻己音は袋から言われたアイスを取り出し、黒に渡す。
「急ぐぞ黒。アイスの灯火が消える前に」
「おい、俺のすでに灯火消えかかってんだけど」
黒のアイスは少し軟らかくなっていた。
失踪現象とアイスの寿命
麻己音と黒を置いて先に廃墟に入っていた5人は、現在二階の廊下を歩いていた。
「結構広いな」
「此処は元学校なのよ。随分前にお亡くなりになってるけど。廃学校よりあたしは廃ホテルの方が好きなんだけどね」
「それはお前だけだ」
「そんなことないわよ。世の中には廃墟マニアなんて者もいるらしいからね」
「見える俺からしたら全く気持ちの分からねぇ性癖だ」
「それはあんたが力強すぎて霊に襲われるからでしょう。のわりにはぶっ飛ばしてるじゃない。霊のこと」
「言っとくが、向こうが襲ってくるからぶっ飛ばしてるだけだ。一通じゃねぇからな。つーか、さっきから霊の気配感じねぇんだけど。本当にいるのかよ」
「そうなのよー。でもあたしが来た時には既に気配感じなかったわね」
詠里は腕を組んで考え始める。
「お前は一番最後に来たじゃねぇか。俺が着いた時には、火夜とジャックがいたな」
「あら、じゃあ火夜がジャックを連れて来てくれたのね。ねぇ、火夜」
詠里は後ろを歩く火夜に声をかける。
視線も少し後ろに向けた時、とあることに気づいた。
「あら、いない」
「あ?」
詠里が立ち止まったので、朔羅も止まって振り向く。
二人の背後を歩いていた筈の火夜、政宗、ジャックの3人がいない。
「…いつからいないんだろうな」
「さぁ?一階の保健室を出た時はまだ全員いたと思うけど」
二人は一瞬視線を合わせる。
目の前には薄暗い廊下。
「おい、これ…」
「大丈夫でしょ。あいつらだし」
「あいつらの心配はしてねぇよ。まさか、一人一人バラバラになるってことはねぇよなって心配だ」
「それは確かに危ないわね。作者が上手く一人一人の話を書けるのか」
「あぁ、それは確かに危険だ」
朔羅と詠里は頭を抱えた。























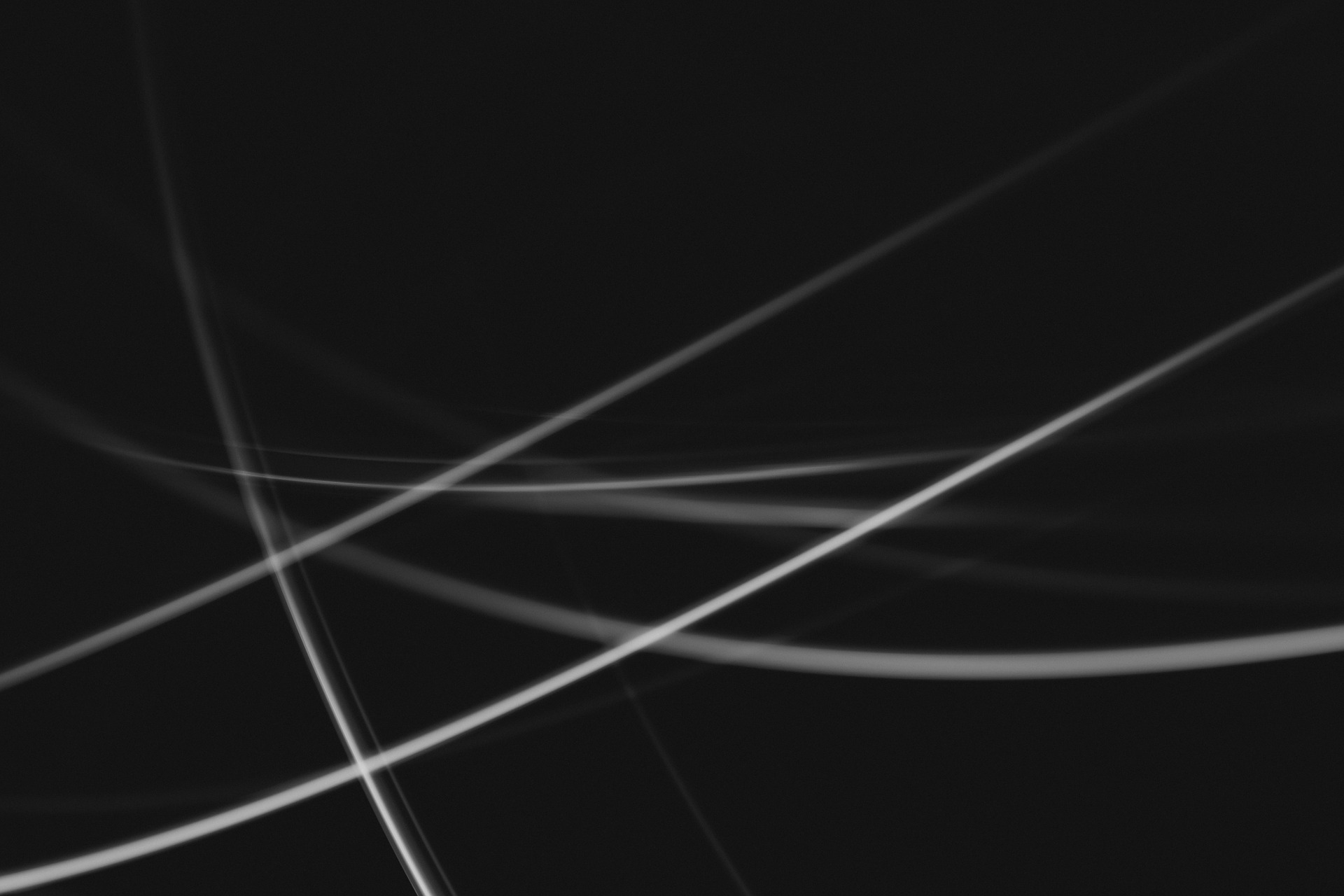










怖かったです。
句読点が多すぎて少し読みづらい。
ちょっと意味がわかりづらい
忘れられない修学旅行に、なりましたね。
ちょっとメンヘラっぽい文章がいいね