・・・それから季節は秋から冬に移った頃のことです。
その日も私は彼女と学校の帰りを同じくしていました。
彼女は、やはり美しいのでした。
紅いマフラーに、グレーの毛糸手袋。
そして乳白色の八重歯を覗かせながら私に微笑みかける彼女。
冬風が二人の間を抜けていきました。彼女の美しく長い髪がたなびきます。
たなびいた髪が眼に入ったようで、目元をくしゃっとさせながら、彼女は髪を整えました。
その仕草も可愛らしいのです。
それにしても、仄暗い町を彼女と共に過ごしていると、なんとも幻想的な気分になります。
・・・しかし視界に、とある電柱を認めたとき、私は一瞬固まりました。
その電柱には、葬儀の案内看板が括り付けられていました。
いつかのおぞましい光景が頭をよぎります。
ところがそれは、こう言ってはなんですが、
いたって普通の葬儀の案内看板でした。
彼女との会話に気持ちを切り替え、電柱を通り過ぎます。
「あ、ちょっと待って!」
彼女は私を引き留めました。
そして彼女は電柱の前まで歩み寄ります。
案内看板に向き合った彼女は、おもむろに、自分のカバンに手を差し込みます。
そして、1枚のポラロイド写真を取り出しました。
・・・写真は、丁寧に、私の彼女の手で、看板に貼り付けられました。
「さ、行きましょう」
彼女は私の血流の止まったような手を、柔らかにつかみ、何事もなかったように歩みます。
・・・私は彼女の顔を見ることができませんでした。
夜の帳はすでに降りています。
私はもうこの闇から抜け出せないように思いました。
・・・それからどのように家に帰ったのか曖昧です。
後日、彼女に先日の出来事の真意を訊ねました。
すると彼女は、私を彼女の家に招いてくれると言うのです。
・・・放課後、気まずく思いながらも、彼女と一緒に帰りました。
「突然に家に行っても、親御さんは大丈夫なの?」
「大丈夫よ。お父さんは単身赴任でいないし、おふくろは・・・あたしに無関心だから。」
「え?おふくろ?君が言うと似合わないなぁ。
ママとか言いそうなのに。」
「そうかしら?あたし、この呼び方好きなのよ。
普段はぶっきらぼうで距離があるようなのに、芯のところでは愛情でつながっている。
そんな温かみを感じるじゃない?
もし将来子供ができたら、子供にもあたしのことはおふくろって呼ばせたいわ。」
・・・この子は母親からの愛情に飢えている。
でも、それは片想いなのだ。そう感じました。
そのあとも、彼女とたわいのない会話を続けましたが、
それでも私の心のもやは消えず、
彼女と手をつなぐことはできませんでした。
ただただ潮風の香りにだけすがりました。
やがて彼女の家に着きました。
廊下を通ったとき、居間に彼女のお母さんがいるのを認めたので、
廊下から軽く挨拶をしましたが、
私達には興味ないようで、見向きもしません。
・・・私達は廊下の奥にある彼女の自室に入りました。
初めて入る彼女の部屋。
しかし高揚感はありません。
ただただ重い気分です。
対照的に、彼女はとても嬉しそうです。
彼女は梅昆布茶を淹れてくれましたが、私はそれに手をつけることはできません。
そして、意を決して彼女に、先日の写真のことを尋ねました。
すると彼女は少し照れた顔で
「うん・・・あなたにまた褒めてもらいたくて・・」
「え?」
「あの写真があれば、通行人の人も、どんな人が亡くなったか分かるでしょう?
痩せている人なのか・・顔にホクロのある人なのか・・目が二重の人なのか・・・
名前だけではただの記号よ。でも写真1枚あるだけで、あの看板を見た人は、きっと亡くなった人のことに想いを馳せるはずよ。」
そう語る彼女の顔は美しく、眼の奥の光はなお輝いています。
「そのために、君は故人の写真を看板に貼ったんだね?」
「そうよ。みんなが見知らぬ故人を偲ぶようになったなら、もっと優しい世の中になると思うの。」
彼女は両手を広げて、天井を仰ぎます。
演劇じみていると思いながらも、ブラウスの袖がなびくのが華麗と感じてしまいました。
「それに、あたしだけ葬儀看板の名前だけを見て寂しい気持ちになるなんて、
・・・あたしが可哀想じゃない?」
彼女は両手を広げながら、顔だけこちらに傾けます。
柳のような美しい眉が、八の字に傾きました。
「あとね、なによりね。
あなたに、優しい子だって言われて嬉しかったのよ・・・」
媚びるような笑みが、彼女のみずみずしい唇からこぼれ落ちます。
私は何も言えなくなりました。
私のへつらいのような褒め言葉が、彼女を変えてしまったのでしょうか。
そして私は、愛する恋人の暴走を受け入れるのも、人間の器なのではと考えてしまいます。
「たしかに、普段テレビで、
紛争や自然災害により何千何万という人が死んでいるという報道を見聞きしているけれど、
正直なところ、ただの数字でしかないよね。
・・・そこに、人の体温を感じることができない。
・・・君は、そんなボクみたいな想像力の無い人達を、良い方向に導いてくれるのかもね。」
それっぽく、私は彼女をフォローすることにしました。
私の、彼女の思想への賛同を聞くと、
彼女は眼を爛々と輝かせます。
「ありがとう!本当にあなたを恋人に選んで良かったわ!」
彼女は満面の笑みです。
私は、その魅惑的な笑顔に心を奪われました。
・・・そうだ。私こそが彼女の唯一の理解者になるんだ。
愛する彼女の、美しい彼女の親愛の笑みを、
唯一間近で受ける恩恵にあずかれる、この私こそが・・・



























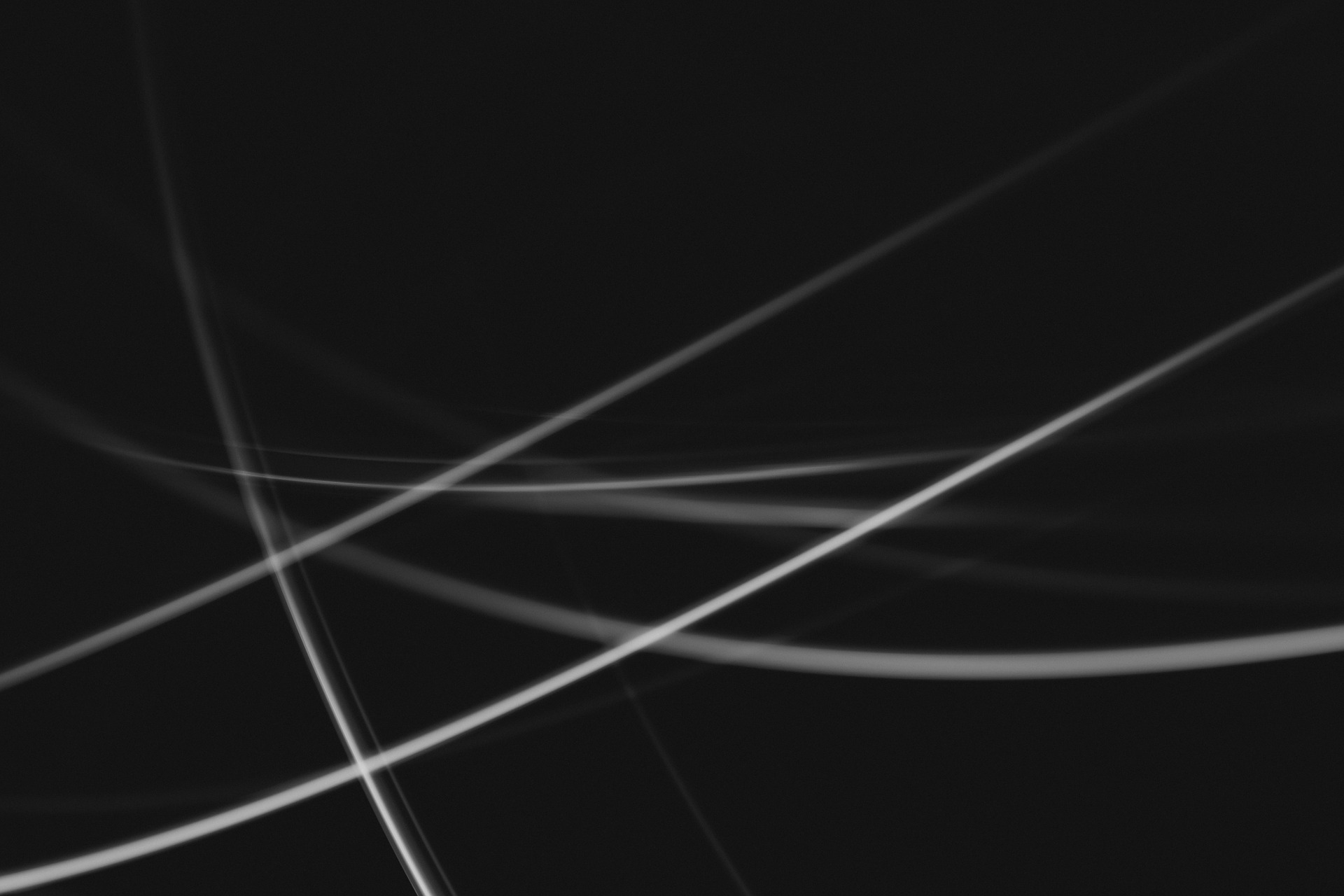








※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。