地方のどでかいドラッグストア。そこでいつものようにアルコールを摂取するためだけの酒を買った。そしてまだ店の自動ドアを出て数歩の距離だというのに、購入したばかりの4ℓ大容量ウイスキーボトルの封を開け、辛抱たまらず一口含んでしまう。つくづくアル中だ。自嘲する。
定職に就かず、恋人もいない。
空気の入ったペットボトルを、意味もなく手でベコベコと揉みながら、だだっ広い駐車場を練り歩く。
「ブゥーン! ブゥーン!」
音の方向を振り返れば、駐車場の端からオンボロな白い軽トラックがエンジンを吹かしていた。しかも、ハイビームでチカチカこちらにパッシングまでしてくる。
煽ってやがる。誰だ?
運転席を見れば、誰も乗っていない。無人の車なのだ。
どういうことだ。自動運転機能の誤作動ってやつか?
こちらの思考が纏まらぬうちに、あろうことか軽トラは一直線に自分めがけて突進してくるではないか。
咄嗟に一目散に逃げ出した。
しかし、片手で重量のあるウイスキーボトルを持っているせいで思うように走れない。バランスが悪い。やはり再来週分に、もう一本買っておけばよかった。
振り返れば軽トラはすぐそこに迫っていた。
ふと酒を捨てて逃げれば良いじゃないかと気づくが後の祭り。コンクリート製の壁まで追い詰められてしまった。
軽トラゆっくりとこちらへにじり寄って来る。無人の車に圧殺されるだなんて。
だが、なぜか軽トラは無意識に突き出されていたウイスキーボトルに、車体の前面を触れては引いてを繰り返している。さながら仔犬が興味のあるものに、鼻先をクンクンと擦り付けてくるかのように。
またワイパーをブンブンと稼働させている。まるで仔犬が尻尾を振っているかのように。
「お前、もしかして」
軽トラはヘッドライトをチカチカ上目遣いにパッシングして、こちらの様子を伺っている。
「懐いてくれてるんか?」
カッチ、カッチと目をパチクリするようにハザードがたかれた。
こんなアル中に、温かみを思い出させるようなことをするな。
そんなの、ズルいじゃないか。
「うちに来るか?」
「プォー!プォー!」
軽トラは歓喜のクラクションをけたたましく鳴らした。
「嬉しいか。ところで品種は……」
どこの仔なのかと、車体の正面に目をやる。しかし、そこにメーカーのエンブレムは無かった。
「……雑種なのか。」
「プォー!」
軽トラは怒ったようにクラクションを鳴らした。
「すまん。これからよろしくな。」
笑えた。
酒に溺れた日々を送って以来、はじめて笑えた気がした。
こうして、この軽トラとのハートフルな日々が始まった。
公園に、海に、ホームセンターに。色んな所に一緒に走り回った。
酒は、辞めた。できるだけこいつと一緒に過ごしたいからだ。
仕事を、始めた。こいつを養わなきゃいけないからな。
しかし、驚いたことがある。この不思議な軽トラは食事を摂らない。餌代がかからないのは飼主想いとも言えるだろうが。
とはいえ、燃料メーターの表示がずっと空を指しているのもいただけない気がする。
そこで、近所のガソリンスタンドへ訪れた。
「ええと……軽トラだから、軽油を入れれば良いんだよな……」
ところが、給油口に軽油のノズルを差し込もうとするが、何故か固く給油キャップを閉じて抵抗し、なかなか挿れさせてくれない。
「オイ馬鹿この! 軽トラには軽油じゃなくて、ガソリンを入れるんだよ!」
隣で給油をしていた農作業帰り風情の婆さんに怒鳴られてしまった。
「そうだったのか……」
あらためてレギュラーガソリンのノズルに持ち変える。今度はあっさりと挿入させてくれた。そして燃料タンクがパンパンになるまでガソリンを注ぎ込むことができた。これで一件落着だ。
またある日。この軽トラにも名付けをすることにした。
いつまでも『軽トラ』呼びでは精神的虐待だ。
「さて、なんと名付けるか。軽トラ……ケイトラ……ケイ……トラ……ケイ……これだ!」
この名付けをきっかけに、この甘えん坊との心の距離は、更にぐっと縮まったようだ。
それから、幾日かの月日が流れた。本当に輝きに満ちた日々だった。
しかし、あまりにも突然に幸せは終わった。
とある大雪の夜、雪見をしようと、実家の程近くにある雪見の名所に向かうべく峠道を走っていた。田舎の峠道であるから本当に暗い峠道だった。
しかし、不意に進行方向の正面から強い光を向けられ、急ブレーキをかける。
警官だった。助手席の窓を開けて対応する。
「検問です。御協力お願いします」
検問か。しかし問題ない。何一つとして後ろめたいことは無い。
「あれ!? この車、ちゃんと車検は通ってますか?」
虚を突かれた。
シャケン? シャケンってなんだ?
いや待て。噂に聞く、あの『車検』のことか。
どう答えたら良いのだろう。駄目だ。わからない。
戸惑いの様子を見てとった警官は、不審そうな表情を向ける。
「……失礼ですけど車から降りて貰えますか?」
警官によって車外へ出される。そして警官は無線でナンバープレートの照会を始めた。
照会自体はすぐに終わったようだ。
だが、警官の目はますます険しくなっている。
「これ、事故車ですよね。しかもそのあと行方をくらませている車だ。あなた、この車をどこで手に入れたんですか?」
「……事故車?」
自分の知らない、こいつの過去。
知られたくない過去を暴かれた愛車は、辛そうにヘッドライトをロービームに伏せていた。
「免許証を見せてもらえますか?」
「え? 私、運転免許の資格なんて持ってませんよ?」
「……それって無免許運転しているってことですか?」
いよいよ犯罪者に対するかのように凄んできた。
しかし、この警官は、何を的外れなことを聞いてくるんだろうか。
「いや、だから、そもそもに私は運転してないでしょうが。」
「は? あなた何を言ってるんですか。車の前列には、あなたしか乗ってないんだから、いったい誰が車のハンドルを握って……え?」
警官は車内を見て固まった。
「私が乗っていたのは助手席ですよ。外車ではあるまいし、常識的に考えて、左ハンドルの軽トラがあるわけないじゃないですか。」
「え、いやだって、この道を走ってきたじゃないですか!?自動運転機能?」
警官は明らかに狼狽している。うむ。今がチャンスだ。
「完全自動運転機能の車なんて技術的にまだ無理に決まっているでしょうが! メルヘンじゃあるまいし、なに夢物語を言ってるんですか。それでは、急いでるんで、もう行きますよ」
混乱に乗じて、警官の横をすり抜けて助手席に戻ろうする。
が。駄目。警官に腕を強く掴まれてしまった。
「待て、まだ話は終わってないぞ」
警官の指先がメリメリと肉にめり込んでいく。
「痛い痛い!」
苦痛の叫びが出る。
その時だった。
「プォー!」
猛烈なクラクションが周囲に鳴り響く。
「誰も乗っていないのに!?」
警官は突然のことに驚愕した様子だ。
「ブゥーン!」
クラクションに続いてエンジンも怒り狂いだした。
激しく警官を威嚇している。
そして車体は警官に迫る。
警官は悲鳴をあげながら尻餅をついた。
……分かるよ。あれ怖いんだよなー。
いや違う。大変だ! 早く鎮めないと!
「駄目! 人を襲えば、この飼い主には管理不可と行政に判断される! 一緒に暮らせなくなるんだぞ!!」
言葉が伝わったのか、車体はピタリと止まった。
「それに他の貰い手なんか、そうそう見つからないぞ。勝手に動いて人を轢こうとする車なんて……あと雑種だし」
しんみりとした雰囲気が周囲に満ちるが、警官は戸惑いを隠せないようだ
「おい……いったいなんなんだ。アンタもその軽トラも何なんだよ!? とにかくその車は確保だ!!」
そう言い放つや、腰の警棒を引き抜き、またも横暴を働こうとする。
「だめだー!」
咄嗟に警官にしがみつく。
無我夢中だった。
「逃げるんだー!!」腹の底から叫んだ。
「!!!」
それに呼応するが如く、たちまち車体は発進し、暗い峠道を突き進んだ。
しかし、少し進んだところで、突如として止まった。
「なにしてんだよ! さっさと行っちまえー!」
そのとき不意に、車体後方のブレーキランプが光った。
1.2.3.4.5……5回点滅した。
「……ユ・ル・ス・マ・ジ だと!?」
メッセージを伝え終えた車は再び動き出し、夜の闇へと消えていった。
「いや、サ・ヨ・ウ・ナ・ラのサインじゃね?」
元凶の警官がなにやら訂正を入れてきた。
だが、もう耳に入らない。
「うわあああああああ!!!!!」
悲しみの慟哭が暗い峠道に鳴り響いた。
……それから、また奈落のなかを暮らすようになった。
自分はいったい何のために生きているのか。
愛する物を失った悲しみを無理矢理に掻き消すべく、みずから仕事に忙殺されにいくような日々を送る。
そんな、ある日のことだ。いつものように深夜まで残業をしているときに、携帯に母から電話がかかってきた。
いつぶりだろうか。何かあったのか?
内容を聞いてみれば案の定、実家の道向かいに住む親戚すじの家で不幸があったのだという。
すぐに残業を切り上げ、とにもかくにもタクシーを拾い実家に向かった。
車中で喪服や香典をどうするかなどあれこれ考えていると、いつのまにかタクシーは見知った峠道に差し掛かっていた。
あの峠だ。ちょうど一年前に、この道を通ったんだっけな。
窓を開けると峠の風が入り込んできた。車内の暖房が効き過ぎているのもあってか、冬の峠の冷気はひんやりと気持ちいい。
幸せだった日々が想起されていく。 アイツと一緒に行った公園、海、ホームセンター。他愛もないようなことが、僥倖だったと思う。
「お客さん、私もその曲好きなんですよ!」
タクシーの運転手が初めて口を開いた。どうやら無意識に口ずさんでいたようだ。
「突然すみませんね。実はこの辺りに幽霊が出るって噂があるものですから、私も怖くて。」
運転手は弁解する。
「良いんですよ。こちらとしても少し感傷的になっていたから。しかし、その幽霊の噂が気になりますね」
「……あれは半年ほど前です。この辺りで検問をしていた警官が行方不明になりましてね。当時は神隠しにあったなんて噂もありました。しかしですね、その警官が幽霊になって夜な夜なこの峠で検問をしているんだそうですよ」
……怖いと言いながらもなかなかに語り口は滑らかだ。この運転手、実は案外好きものなのかもしれない。それにしても半年前なら、自分が検問を受けた後のことか。
確か検問を受けたのは、あのあたりで……あれ?
「運転手さん、前……誰か立ってませんか?」
進行方向の先。ヘッドライトに人影が照らされていた。タクシーが近づくにつれ輪郭がはっきりしてくる。警官だ。検問か?
しかし、様子がおかしい。赤色灯は夜間だというのに点灯されていない。制服についても、遠目で分かるほどに傷んでいる。
出た。先の話に出た警官の幽霊だ。
タクシーが近づくにつれ、警官姿のそれは、ゆらゆらとタクシーの前に立ちはだかった。
いかに幽霊とはいえ、警官姿の人間を車で轢き進む胆力を、この運転手は持ち合わせていなかった。諦念の嗚咽を漏らしてからタクシーを停車させてしまう。
警官は無言のままフロントガラスに顔を近づけて運転手の顔を眺めた。
それから、ぼろぼろの制服を車体に擦らせながら、顔を後部座席のドアガラスにまでスライドさせ、チラリとこちらの顔を確認する。
その途端、警官は急に目を見開き、半開きの窓の隙間に強引に腕を差し込んできた。
咄嗟に隣の座席に身を翻し、警官から間合いを取る。
カチッ……ガチャリ……
爪の剥がれた指によりドアは解錠され、開け放たれた。
警官は車内に侵入した。
しかし、じっくりこちらの顔を確認すると、なぜか驚愕の表情に変わった。
そして、急いでタクシーから降りるや腰を直角に折り曲げて深々とお辞儀をする。
「……お待ちしておりました。」実にかしこまった声だった。
「どうぞ……こちらへ……」警官は五指をしっかり伸ばし、まるで重要ゲストを案内するかのように、うやうやしく車外へ出るよう促してきた。
わけがわからないが、こちらに危害をくわえる気はないようだ。しかもどうやら幽霊というわけではないらしい。
導かれるまま車外に出て、警官にホイホイとついていく。
ひらけた敷地があり、そこに一台の白い軽トラが停められていた。
あの懐かしい軽トラを見間違えるわけがない。
「プォー!」
ひとりでに軽トラのクラクションが鳴った。思わず軽トラに駆け寄ろうとする。
だが、その瞬間、警官が脱兎の如く走り出し、軽トラにすがりつく。
「ごめんなさい。ごめんなさい。いえ、滅相もありません。失礼なことなど一切しておりません。」などと必死に弁明をしながら、懐からだしたスポンジで車体を磨き出した。
久しぶりに再会した我が軽トラは、見違えるほどにピカピカになっていた。
それは別に良い。しかし、この状況はいったい……
「プォー!」
怒声のようなクラクションが鳴った。
「は、はい! 直ちにお通し致します!」
そう言うや警官は助手席のドアを急いで開けた。ところが勢い余って、ドアの端が岩壁にあたってしまった。
「ひい、ごめんなさい。どうか、わたくしめに教育をお願いします」
そう言い終わるや警官は車体後方に回り込み、排気ガスが出ているマフラーに口を近づけて、ガスを吸い込もうとする。
「プォー!」
「え、今回は見逃して頂けるのですか!?」
そして警官は、こちらに手招きをして、助手席に座るようにうながしてくる。車内を確認してみれば、内装こそ変わっていないが清掃が行き届いており、まるで新車のようだ。だが、逆にそれが不気味でさえあった。
それはさておき、久しぶりに愛車の助手席に座ることができた。思わず胸が熱くなる。
警官は、この再会の様子を見届けると
「それでは、私はこれにてお暇をいただきます……」と、そそくさにこの場から退場しようとする。
だが
「プォー! プォー!」
「え……いくらなんでも、そんなこと出来ませんよ。勘弁してください……」何を命じられたのか、警官は泣きそうな顔で慈悲を哀願している。
「プォー!」
さも指示に背く事を断じて許さぬ、と言っているかのような強い音調でクラクションが鳴り響く。
警官はその場に泣き崩れた。
それから絶望した表情を浮かべながらボロボロの制服を脱ぎ始め、ついには真冬だというのに全裸になってしまった。
そして軽トラの正面に立ちはだかり、その場で土下座する。
「わたくしめのせいで、お二人の仲を別つこととなってしまい……誠に……誠に……申し訳ありませんでした」
……警官の謝罪が終えると、車はひとりでに、ゆっくりと前進した。
「おい!」
まさかの発進に、思わず声が出た。
ガダン!
土下座する警官の後頭部と背中を、タイヤは無慈悲に踏み越えていった。
恐る恐る後ろを振り返る。
警官は土下座の姿勢のままピクピクと痙攣していた。
やがて愛車は峠を越えて、とある廃車置き場に停車した。
いつのまにか周囲は大雨だ。実家に行かねばならないが、もはやどうでもよくなってきた。とりあえず母親に電話する。
「もしもし母さん? 俺だけど」
「……ちょっとあんた、いまどこにいるの!? 葬儀の準備を手伝ってもらいたいんだから早く帰ってきなさいよ!」
「うん……ごめんね。俺、その葬儀は、もういいや。」
「は!? ちょっと慶太郎! あんた急に何を馬鹿な事を言ってるのよ!? いいから早く帰ってき」母親は何か言いかけていたが、俺はブツッと電話を切った。
……すべてが面倒だ。助手席の背もたれを倒し、目を閉じる。
「俺はさあ、お前とこうして過ごせるなら、ほかに何も要らないよ。お前もそうだろ? なあ、『トラ』」
そう、天井に口ずさむ。
だんだんと眠くなってきた。

























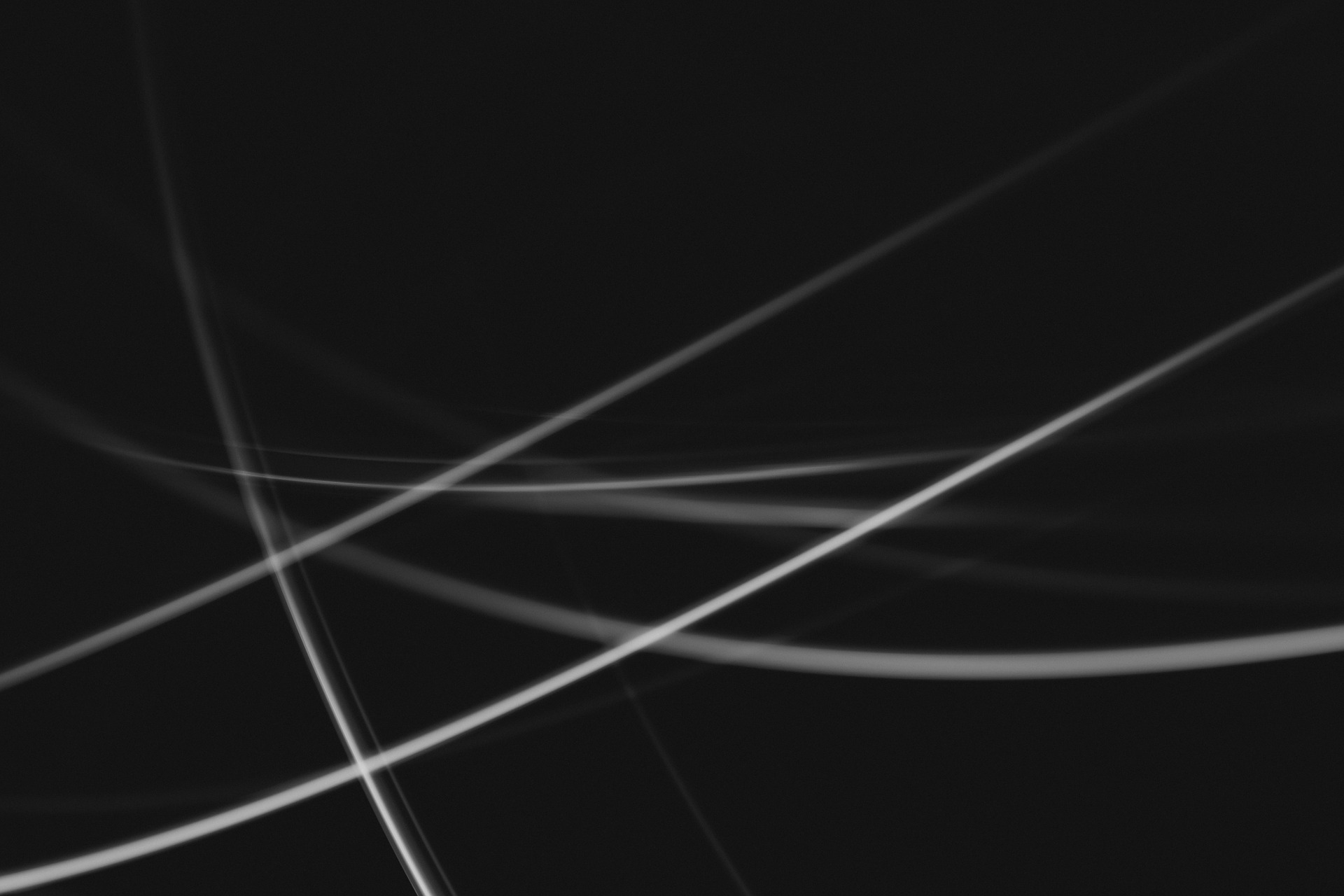








思ってたのと違った〜
トラなのかケイなのか