「お前は黙っていなさい。誰もそんなことは言っていない。…お見苦しいところをすいません。どうぞ、続けてください」
「えぇ、それは赤ちゃんハウスを漂う水子の霊達が共通に持っていた思い、願いとも呼べるものに関係しています。それは『この世界に生まれたい』という非常に強い思いです。私はあの場所で確かにそれを感じ取りました。その思いを遂げられる、願いを叶えることのできる存在がこれから生まれてくるC君だったのです」
「だったらなぜ…なぜ、Cは死んでしまったのですか?あなたが最初に言った通りならば、その幽霊の生まれたいという願いは叶ったのでしょう?おかしいじゃないですか?」
「………私が半日ほどあの場所にいてようやく気が付いたことがあります。水子達の共通した『生まれたい』という願い、それは本当の願いではなく、あくまで手段としてのものだったのです。その奥底にあった本当の願いは『おかあさんに会いたい』というものです」
「赤ん坊というのはおなかの中にいる頃から、母親の体温、声、愛情といったものを感じ取り、生まれるずっと前から母親のことを知っているのです。C君にとり憑いた水子達は生まれることができました。ですが、目の前にいたのは自分の母親ではありませんでした。Aさんが水子達の母親に似ていた場合もあったでしょうが、C君に憑いていた水子は複数です。Aさんがその子達全ての母親と重なるはずがありません。ですから、その子達はずっと探していたのです、自分の母親を。C君が亡くなったのは母親を探そうと外へ出たことによる事故で間違いないでしょう。………私は自殺であったとは思いたくありません。ですが、遅かれ早かれC君は母親を探しにどこかへ出て行ったでしょう、そして似たような結末が待っていたはずです。言いにくいことですが結末は最初から決まっていたのです」
どれだけの時間が経ったか分からないが、スズの両親が息を切らしながら病院へ入ってきた。私はただ「そこの診察室です」と一つしかない診察室の方を指さした。それからしばらく経ち、校長がやってきてスズの両親が来たことを伝えると、校長はそのまま診察室の中に消えていった。ケンは一緒ではなかった。少し時間が空いてまたドアが開き、佐野先生がやってきて私の横に座った。そのまましばらく佐野先生は無言で座っていたが、「何か飲むか」と私に声をかけてきた。私はいらないと答えたのだが、佐野先生は自動販売機の方へ歩いて行き、戻って来ると私に水の入ったペットボトルを手渡した。私はふたを開けてそれを一気に飲み干した。飲み干した水に内臓が溶け込んでいくような妙な感覚だった。
診察室から出てきた校長は佐野先生を呼び、何かを話していた。校長は話しを終えると私の方へやってきた。「これから佐野先生がお家まで送って行きます。明日は一日病欠ということにしますので、お家でゆっくり休んでいてください。お家の人には佐野先生が話をしてあります」そう言うと校長は廊下の奥の方へと歩いて行き、真っ暗闇の中へと消えていった。
「行こうか」佐野先生は私の肩に手を乗せ、出口の方へと歩き出した。永遠の終わりという訳の分からないものに対して私は別段、寂しさや喪失感を感じていなかったようで、私の足取りは思いのほか軽い。私が佐野先生の車に乗り込んだ時、時計は深夜0時を指す少し手前で、夜の街中は死んだようにひっそりとしていた。あまりに静かなそれは、どこか別の世界、それこそ死の世界のように思われ、車のエンジン音と佐野先生の吸うタバコの匂いがかろうじて私をこの現実の世界に繋ぎ止めているようだった。
「早期流産だそうだ」佐野先生が唐突に口を開いた。
「激しい運動と精神的なショックが原因じゃないかと医者は言っていたが、妊婦の15%は流産するものだから断定はできないそうだ。公園での苦しみ方が尋常じゃないから明日色々と検査をするらしい。ただ、今の状態ならば命の危険はないとも言っていた」
私は返事もせずに無言で窓の外を眺めていた。街並みを抜け、ガラス一枚を隔てた死の世界はより暗く淀んだものになっていた。
「先生、先生は結局幽霊を信じていますか?」
「化学の教師にそういうことを聞くか?」
「俺、思うんですよ。スズが死なずに済んだのは、とり憑いてた赤ちゃんの霊がスズのこと助けてくれたからじゃないかって。その赤ちゃんの霊が死のうとしてるスズのこと引き留めてくれたんじゃないか、なぜだかそう思うんです。おかしいですよね」
「おかしい、おかしくない以前にそういう考え方は、俺は好かないな」
佐野先生は淡々と続けた。
「全てはあの報告書通りに今回のことが進んでいた前提だが、その赤ん坊の幽霊は生まれたいっていう願いをかなえる千載一遇のチャンスを掴んだ。どうやったって報われも救われもしない連中にとって、それは唯一とも言える希望だろう?それを見ず知らずの母親のためにむざむざと自分から手放した、か。ユウにすれば付き合いの長い宮本が助かってハッピーエンドだろうが、陰で俺達が見ることも感じることも出来ない不幸のどん底にいる奴らがより深い不幸に堕ちた。そんな裏側を無視して、能天気に喜ぶのは下も後ろも見ない、のぼせ上った考えだと俺は思う」
車は深い暗闇の中を泳ぐように進み続けた。
校長に言われたように私は一日学校を休み、その次の日普段通りに登校した。学校の様子はいつもと変わらず、佐野先生は私に体調のことを一言、二言聞くだけで、特段変わった様子はなく、いつもと変わらない佐野先生だった。私は放課後、校長室へ呼ばれた。
校長室には校長しかおらず、校長はあの日と同じ様にソファに腰掛けるよう私に言い、一枚の紙を差し出した。何かこまごまとしたことが色々と書いてある用紙の中央には「不問とする」とだけ書かれていて、よく見てみると用紙の左上には私の名前が書いてあり、右上の評議者という項目の横に校長と佐野先生の名前が書かれていた。
校長が説明するには何かしらの処分を決定したときに、この様式の通知書を手渡しするのだという。「不問」という文字は私が無罪放免であるということを示すと同時に、あの日の出来事に終わりが告げられたことも意味していた。つまり、この薄っぺらで、ちんけな紙が終幕のエンドロールというわけだ。校長はケンとスズについては何も触れず、私も触れようとはしなかった。ケンとスズの名前がなくともエンドロールは流れ終わったのだ、白いスクリーンはこれ以上何も語らない。
校長は緑茶を注いだマグカップとちょっとした茶菓子を部屋の隅から持ってきて私に勧めた。私は素直に受け取り、ゆっくりとマグカップに口をつけた。校長は対面のソファに腰掛けて、私に何か話しかけられるのを待っているように黙っている。私は車の中で佐野先生に話したことを校長にも聞いてもらった。校長は黙って私の話を聞き、聞き終わると窓の方へ視線を向け、私から顔を背けるようにして口を開いた。
「そういう解釈もあるでしょうね。私は…伊藤君とは少し違って、おなかの中の赤ちゃんが宮本さんを救ってくれたのではないかと思いました。あの時の宮本さんは随分と様子がおかしかった。私は宮本さんの普段の様子を知りませんが、それでも佐野先生と一緒に話をした時の様子とはあまりにかけ離れて…狂人じみて見えました。それはまるで、殺人鬼に追われる映画の登場人物のようでした。宮本さんは自分から死のうとしていたのではなく、迫ってくる死から逃げるようにしていたのでは、そう、とり憑いた水子達が宮本さんを殺そうとしているのではないか」
「私の推測ですが、水子達は気づいていたのではないでしょうか。宮本さんは自分達の母親ではなく、さらには、本当の母親はもう世界のどこにもいないということに。そうであるならこんな世界に生まれたくはない、母体が死ねば自分達は生まれない、そう考えて宮本さんを死なそうとしていたのではないかと。そして母親を助けるために、まだ名前もない赤ちゃんが自分の命を犠牲にしたのではないか、つまりは自殺をしたのだと。分別どころか意識の有無すら分からない赤ちゃんが自殺とは荒唐無稽ですが、大人も子供も大勢自殺をする世の中ですから赤ちゃんが自殺をしてもおかしくはないでしょう…」
一通り話した後、校長は「教育者として適切ではありませんね」と訂正のような言葉を口にした。私は校長の語る言葉をただ黙って聞いていた。誰だって、不幸は第三者の悪意が引き起こすものと信じたいし、その方が、自分が悲劇的結末の一歩手前までを演出した当事者であるなどと考えるよりもずっといい。もっとも、私には校長を責めたり、許したりする資格も権限もなく、懺悔を聞き受けるだけの清廉さを有しているわけでもなかった。スズを救ってやることも、ケンを殴ってやることも出来なかった私は最初から最後までエキストラの如き傍観者でしかなかった。
私はテーブル上の通知書を手に取って校長室を出た。校長室の外には誰もいなかった。そこにはケンとスズが待っていて、私と入れ替わりでほんの少し緊張しながらどちらかが校長室に入って行き、私は大丈夫だよと目配せする、そんな光景を私は心の隅で期待していたのだろう。だが、そこには誰も立ってはいなかった。
二人は消えてしまったのだ。私を残してどこかへ消えた二人、私はあの二人を憎むほど愛していなかった。燃えるような夕焼けが私を照らし、映し出された影はあの深夜の街に似て、全てを飲み込むような底のない暗い色をしていた。
ここから先のことは私の口から語られるべきではないだろう。なにも、私だけの秘め事としておきたいというわけではない。ここから先は本来保管されるべきでない、校長の言っていたことの意味が今なら少しは分かる。一寸先が天国か地獄か、それはまだ足を踏み入れていない人間が知るべきことではないのだ。


























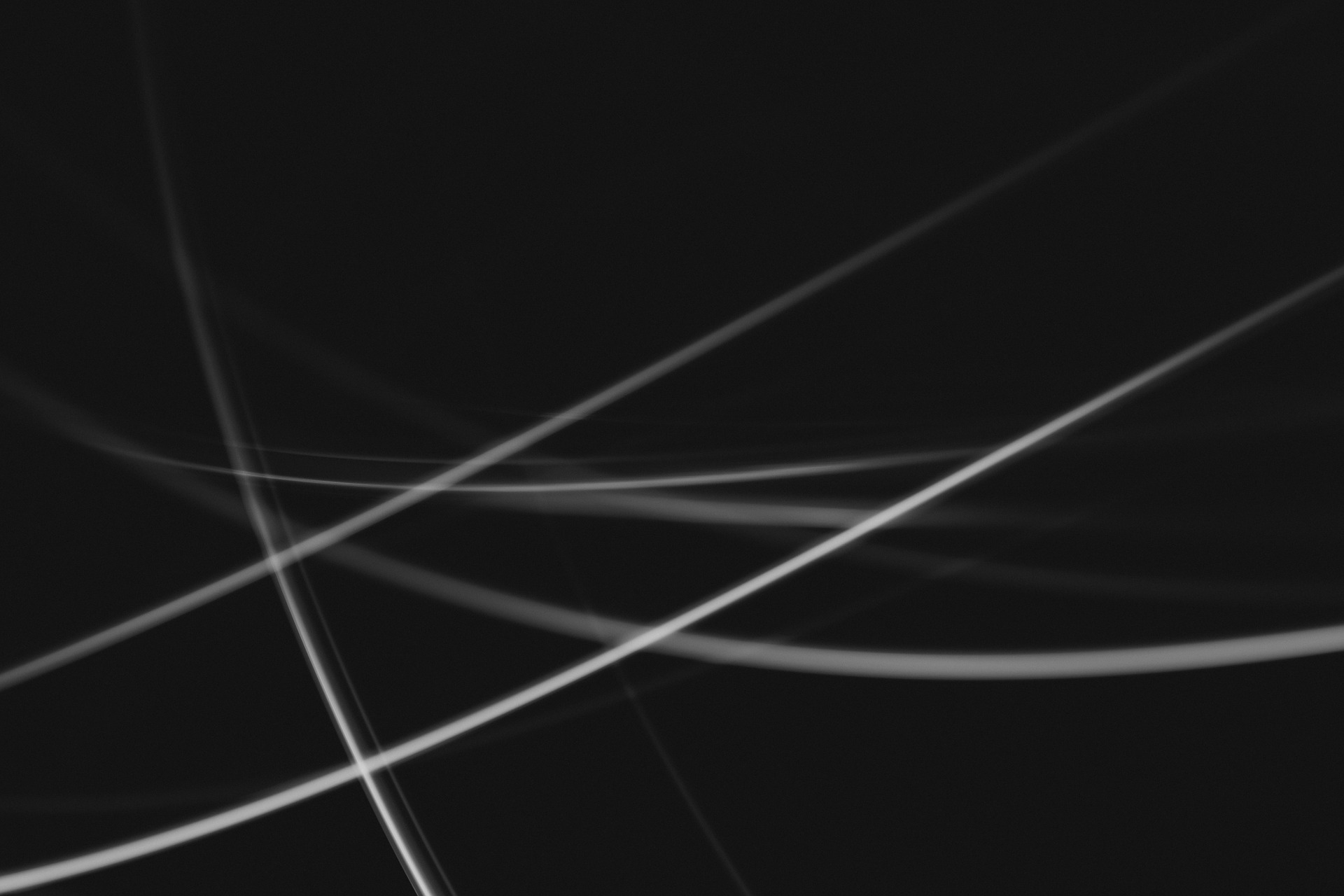















※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。