二月十四日は、血の色をした日です。
比喩ではありません。カカオは予告です。甘さは前触れです。文学的でしょう。私はそういう感性を持っているので。
私はその日、勇気という名の内臓をひとつ取り出しました。もちろん本当に取り出したわけではありませんけど、気持ちとしてはかなり臓器でした。それを溶かして、混ぜて、型に流して、冷やして固めました。手作りです。既製品では伝わらない体温というものがあるのです。
温度管理は恋の基本です。三十八度を超えると分離します。四十五度を超えると壊れます。私は壊れたくないので、慎重に湯煎しました。彼のことを考えながら。何度も温度計をのぞき込みました。数字は嘘をつきません。人間はつきますけど。
放課後、廊下の端で彼を呼び止めました。
べ、別に特別な意味はありませんけど、みたいな顔で。内側では雷鳴が鳴っていましたが、表情筋は制御しました。私は制御できる女です。
「これ、よかったら」
彼は一瞬、ほんの一瞬だけ、顔を歪めました。
眉が動いた。
口角が引きつった。
目が、私を通り越して、向こうの窓を見た。
それだけです。
それだけで、十分でした。
ああ、嫌だったのだ。
重いと思われたのだ。
迷惑だったのだ。
脳内変換装置が、即座に動きました。私は優秀です。たった零・五秒の表情を、絶望へと翻訳できます。
その夜、私は残ったチョコレートを全部食べました。噛むたびに、彼の名前が歯に挟まる気がしました。甘いのに苦い。苦いのに甘い。世界は二律背反でできています。私は知的です。
でも、それでは足りませんでした。
私はノートを開きました。お気に入りの万年筆で、彼の名前を百回書きました。百は区切りの良い数字です。呪術的にも、心理的にも。
インクが滲み、名前は黒い沼になりました。
その上に、包み紙を置きました。指紋と体温と、溶けかけの脂質が染み込んでいます。科学では測定できなくても、結合は起きます。私は理系もいけます。
「あなたは、私を拒絶しました」
そう書きました。
そして、
「だから、私のことを考えるたびに、胸が少しだけ痛くなりますように」
と、丁寧に。
願い事です。
呪いではありません。
願いと呪いは、対象が苦しむことを祈るという点で、ほぼ同型です。構造の問題です。


























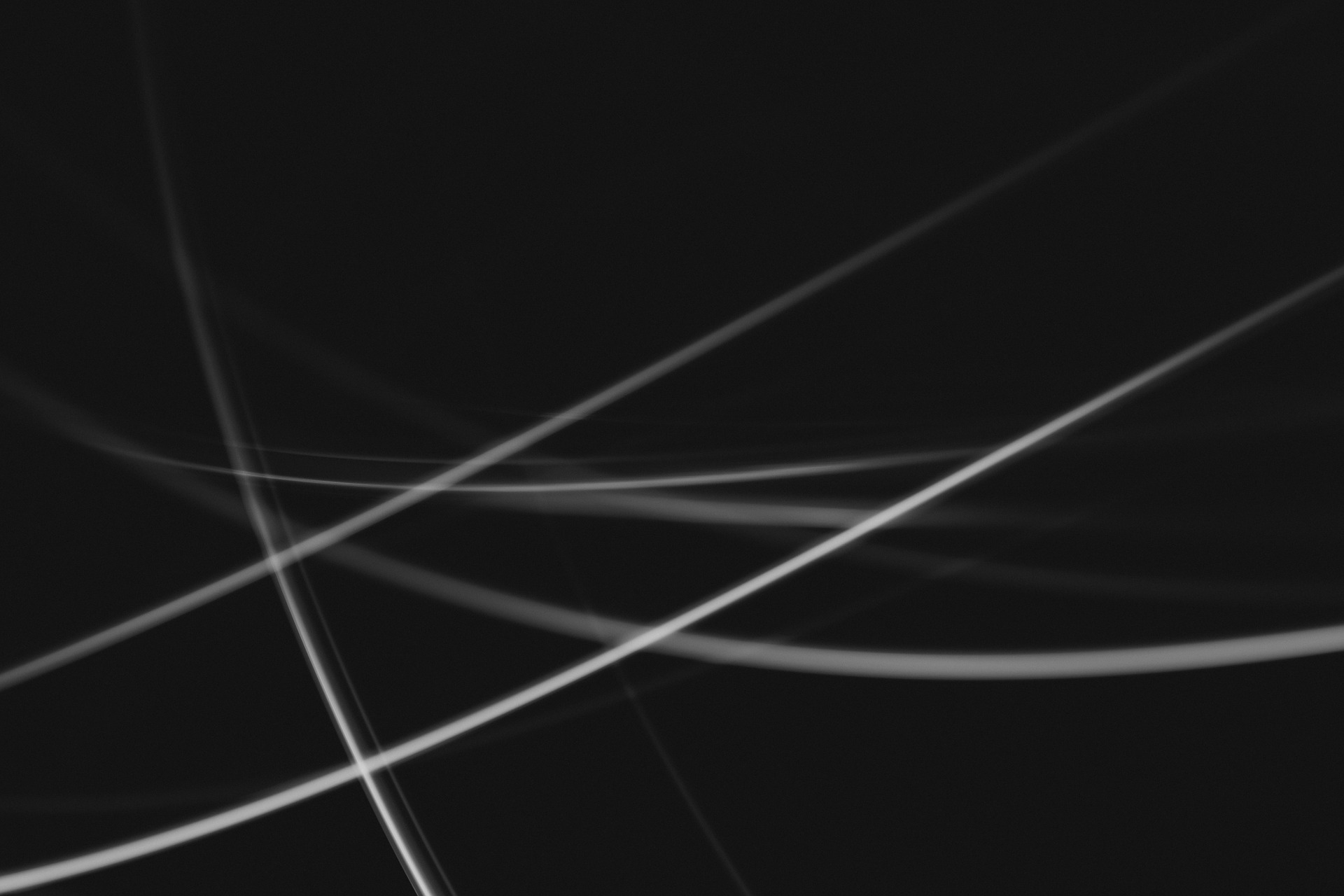



※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。