あれはもう何年前のことだろうか、私が高校3年生の時のことだ。あの時私には2人の親友がいた。友人と呼べる存在は何人もいたが、やはり親友と呼べるのはあの2人だけだった。
1人目の名前はケン、あいつとは2年生のクラス替えの時に初めて出会った。私はインドア派でケンはアウトドア派と正反対な2人だったが、好きな漫画や音楽といった趣味嗜好がぴったりと一致し、すぐに打ち解けて仲良くなった。知り合ったのがわずか1年前だったとは思えない、まるで生まれた時からずっと一緒にいたかのような、ケンはそういう存在だった。
2人目の名前はスズ、小学校からの付き合いで所謂幼馴染だ。小学生の時から一緒に下校したり遊んだり、それが高校生まで続いているのだから中々に長い付き合いになる。大抵、学年が進んでいくと周りの目を気にして異性の幼馴染とは疎遠になっていくことが多いと思う。だが、スズは高校生になっても変わらない笑顔で駆け寄ってきて、やや強引に私を色々な場所へと誘い出すのだった。
ケンと仲良くなった私はスズにもケンを紹介した。2人はすぐに意気投合して、3人でカラオケやゲームセンターなんかによく遊び歩いたものだった。あの時は本当に毎日が楽しかった。私達3人は奇跡とか運命とかそういうもので結びついていて、その結びつきは永遠を感じさせるほど強く、決してほどけることはない、そう信じていた。
私がケンとスズから「恋人同士になった」と聞かされたのは、3年生の夏休みに入る数日前のことだった。私は狐につままれたような顔をして聞いていたが、なんでも、3人で遊んでいるうちに段々とお互い惹かれ合うようになっていき、少し前にあった文化祭の最後にケンの方からスズに告白したらしい。お互いに思っていたことは同じで、晴れて2人は結ばれることとなり、出会うきっかけを作ってくれた私にお礼も兼ねて報告にやってきたのだった。
唐突なことではあったが、私は2人のことが大好きだったので、その2人が幸せそうにしていることをとても嬉しく思った。私は心の底から祝福の言葉を送り「たまには俺も混ぜてくれよ」などと冗談っぽく言ったりもした。2人は「ありがとう」と笑って言い、早速と言わんばかりに私にある誘いをしてきた。
ケンとスズは志望する大学の所在がお互いバラバラで、進学したら中々会えないだろうと思い、この夏休み中にたくさんの思い出を作るべく色々と出かける計画を立てたらしい。2人はそれぞれ行きたい場所を言い合い、行きたいと一致した場所を数か所選び出して目的地に決めていった。だが、その中でお互い行ってみたいと一致しながら、どうしようかと思い悩んでいる場所があった。それは「赤ちゃんハウス」と呼ばれるこの辺りでは有名な心霊スポットだった。
赤ちゃんハウスという名前だが、無論、西〇屋や〇カチャンホンポなどとは無関係で、元がファミリーレストランだったと噂される廃墟のことだ。私達の通う高校からは車で30~40分ぐらいの場所にあるので近場というわけではないが、多くの生徒が知っているであろう有名な心霊スポットである。
この廃墟が有名なのには2つの理由がある。1つ目はその外観が奇抜であること。赤ちゃんハウスは一見すると小さな西洋のお城なのだが、外壁が奇抜な紫色であり、例えは悪いが昔のラブホテルのような外観をしている。画像で見たり見せられたりすると、そのインパクトから、否応なしに赤ちゃんハウスの強烈さが脳内に刻まれるのだった。
2つ目の理由はそこで起こるらしい怪現象の内容が誰に聞いても同じであることだ。その内容は単純明快で「赤ちゃんの声がする」というものだ。誰に聞いても同じ答えが返ってきて、人影を見たとか、ドアが勝手に開いたとか、ラップ音がしたという話は聞いたことがない。なぜ赤ちゃんの声が聞こえるのか、いつ頃廃墟になったかというような細部には種々の噂があって中々一致しないのだが、怪現象の内容については一致している。そこが何とも不気味ではあるが、興味を惹かれる点でもあった。
補足として、赤ちゃんハウスでは過去にとんでもない事件が起きていたという噂話がある。それはレストランとして営業していた時のことで、そこのオーナーと女性従業員が恋仲になり、やがてその女性従業員はオーナーの子供を身ごもった。オーナーには妻子がいたが、「妻とは離婚するから」と言いながら関係を続けた。最終的にはオーナーがその女性従業員を罠にはめるような形でレストランから追い出し、関係を清算したらしい。それからしばらくして、その女性従業員が復讐のために生まれた赤ちゃんをそのレストランの冷蔵庫に遺棄した、そういう内容だ。なので、赤ちゃんの声が聞こえるのは冷蔵庫が置いてあった調理場、そう噂話は締めくくられるのであった。
赤ちゃんハウスの簡単な説明は以上だが、ケンもスズも友人や先輩からその存在を聞かされずっと前から興味をもっていたらしい。いい機会だから行ってみようとなったのだが、2人では何となく不安だということでユウ(私の名前)も誘って3人で行こうと考えたそうだ。私は赤ちゃんハウスになんの興味もなかったが、2人が行きたいと言うなら、と軽い気持ちで「いいよ」と返事をしてしまった。ケンもスズも喜んだ顔で私にお礼を言った。
それから3人の予定を勘案して、夏休みの終わる1週間前の日にしようと日にちを決めた。やはり夜、それも真夜中の方が雰囲気も出るはず、終電の時間もあるので電車は使わず自転車で行こうということになった。予定通りの探索時間でも帰りは深夜になってしまうが、家族には友達の家に泊まるということにしておいて、ファミレスかどこかで朝まで過ごそう、計画は順調に決まっていった。夜通しのサイクリングのような計画内容になったのだが、「それはそれで楽しそう」と、スズは嬉しそうにはしゃいでいたのを覚えている。
赤ちゃんハウス行きの計画が決まってから出発日まで、私は2人と会うことはなかった。時折2人でどこそこへ行ってきたというメッセージが送られてくるのを私は微笑ましく思い、何となく赤ちゃんハウス行きが楽しみに思えてきた。
当日、ケンとスズは私が到着するよりも早くに集合場所へ着いていた。2人は随分と距離が近づいたようで、手を繋ぎながら私のことを待っていたようだ。私はそれを冷やかしたが、2人は照れたように笑い、「早く行こう!」と自転車にまたがった。時刻は21時少し前で、休憩を含め22時30分の到着を目指して私達は出発した。道中、アクシデントなどはなかったが、夜とはいえ8月の田舎道は蒸し暑く、私達は小まめな休憩を余儀なくされた。結局、目的地に着いたのは23時を少し過ぎたころだった。
赤ちゃんハウスがあったのは住宅街と呼ぶには物寂しい場所だった。周囲にはまばらに民家があったが、時間が時間なので通りには人も車も見当たらない。赤ちゃんハウスは大きな道路に面していて、昼間であればいくらかの車通りはあるのだろう、レストランの立地としては悪くなかったはずだ。
私達はかつて駐車場であっただろう草が伸び放題の場所に自転車を停めた。月は出ていたが、周りには街灯が1、2本しかなかったため、赤ちゃんハウスの外壁の様子はよく分からなかった。建物の真正面には、高級ホテルから盗んできたような立派なドアに閉ざされた入り口があった。鎖などで頑丈に閉ざされてはいなかったが、ドア付近の荒れ具合からそれは長い間閉ざされたままなのだろうと思えた。
「正面のドアは施錠されてるから、裏の従業員用のドアから入ろう。そこは開いてるらしいよ」私の前を歩くケンが言った。何でそんなことを知っているのか?と聞くと、この日のために情報収集をしてきたらしい。声の感じからケンは少しはしゃいでいるようだったが、スズの方は少し緊張しているように見え、ケンの腕にしがみつきながら恐る恐る歩いていた。私はリュックから懐中電灯を取り出し、赤ちゃんハウスの方を照らしながらケンとそれにくっついているスズの少し後ろをついて行った。特徴的な紫色はよく分からなかったが、窓が割れないようにするためなのか、窓があると思われる箇所には木の板が頑丈に打ち付けてあり、それが何とも不気味な雰囲気を醸し出していた。
私達は建物をぐるりと回って正面入り口のちょうど裏の辺りへと歩いて行った。そこにはプレハブ小屋についているような簡素なドアがあり、ケンがゆっくりとドアノブを引くと軋む音を立てながらドアは開いた。確かに施錠はされていなかったようだ。ケンはスズの腕を少し引っ張るようにして中へと入って行った。スズは嫌がっている様子はなかったが、やはり足取りは重いように見え、私は急かさないようにスズが建物に入ってしまってからゆっくりと中へ入った。
ドアの先は数メートル程度の一本道の廊下で左手と右手、そして正面にそれぞれドアがあった。左手にあるドアの上の方を照らすと「男子更衣室」と書かれているようだった。ケンはどんどん先へと進んでいて、正面にあったドアを開けると躊躇せずにその中へ入って行った。私もその後に続いてドアを抜けると、その先には同じような造りの廊下が続いていた。左手にはTOILETと書かれたドアがあり、正面には狭い廊下と対照的な開けた、天井の高い空間が見える。ケンとスズは既にその広い空間の場所まで進んでいた。
「赤ちゃんハウスの中って意外と広いんだな。真ん中のあれってなんだろう?」ケンは懐中電灯で周囲を照らしながら独り言のように喋っていた。
私も同じように周囲を照らしてみたが、確かにここは中々の広さがあり体育館二つ分位はあるだろう。室内はホコリっぽいが荒らされた様子はなく、たくさんの円形のテーブルが規則正しく並び、その上には逆さまにした凝った形の椅子が3~5脚ずつ置いてある。窓の数は多いが、板で塞がっているため明かりはほとんどなく、懐中電灯の明かりを頼りにするしかない。私はテーブルの一つに近づいてその様子を見てみた。ホコリが分厚く積みあがっていて長い期間このままの形で放置されていたのだろう、椅子の他には何も置いてなくて、メニューや食器の類というものは見当たらなかった。なぜこんな中途半端な状態なのだろうかなど私は色々と考えていたが、中央の方から私を呼ぶ声がしたので、私はそっちの方へと歩いて行った。
「なぁ、これなんだと思う?」ケンが懐中電灯を向けた先にはホテルのフロントと見紛う立派なカウンターがあった。
「多分ここが会計の場所だったんじゃないか。今はないけど、その上にレジとかが置いてあったんだと思うよ」
「それにしては仰々しくないか?」
「外観がお城だから雰囲気づくりの一環じゃないか?」
「それじゃあ、例の調理場もこういう豪勢な感じの造りなのかなぁ」
「調理場は客から見えないんだから普通なんじゃないかな」
私とケンはしばらくの間室内の様子についてああだ、こうだと話をしていた。しばらく2人で話をしていたのだが、スズが会話に全く参加してこないので、ケンはスズに「どうした?」と声をかけた。思えばさっきからスズはケンの腕に抱きついたまま黙っている。怯えているとか、震えているといった様子ではなさそうだが、何かを言おうとして言い出せずにいるような、そわそわした感じに見えた。
























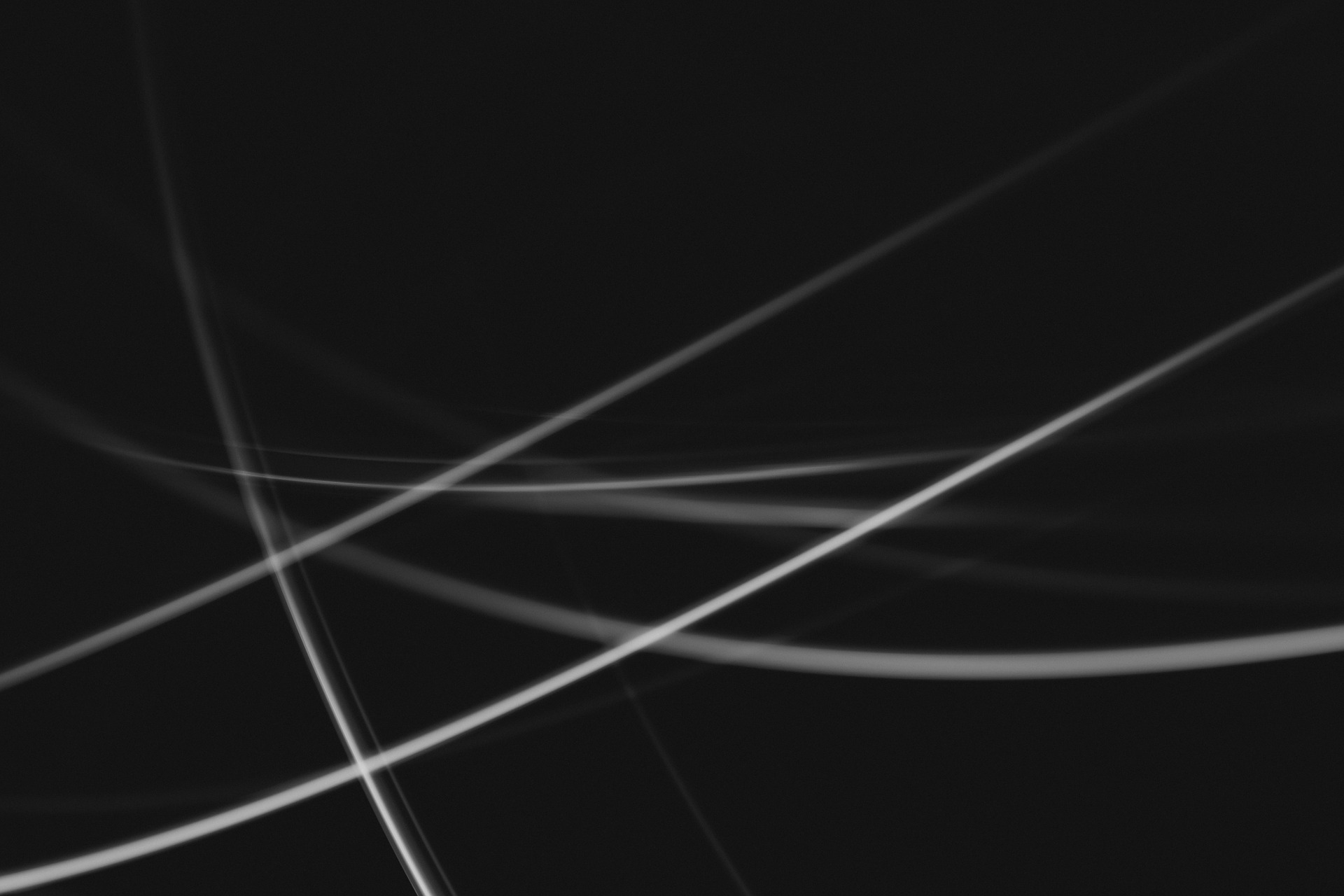















※コメントは承認制のため反映まで時間がかかる場合があります。